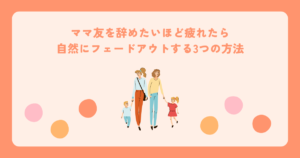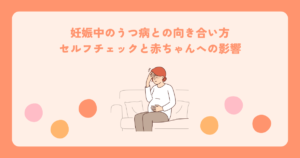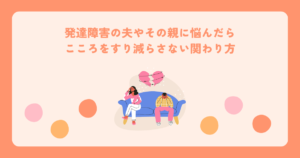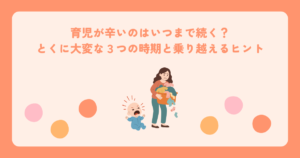赤ちゃんが生まれて、毎日が幸せでいっぱいのはずなのに「なんだか気分が沈んで涙が出てしまう」「イライラして赤ちゃんに優しくできない」そんな風に感じてますます落ち込むママは少なくありません。
出産後は心も体も大きく変化します。気持ちが落ち込み「どうしたらいいか分からない」と感じているなら、それは心からのサインかもしれませんよ。
この記事では、「産後うつかも?」と不安を感じているママがどうすればいいのか、対処法や相談先を分かりやすくお伝えします。
産後うつとマタニティブルーの違い
出産後、多くのママが経験するのがマタニティブルーです。これは、産後すぐのホルモンバランスの急激な変化や疲労、環境の変化によって起こる一時的な感情の揺れです。
この時期は、涙もろくなり、不安や焦りが強くなることも少なくありません。イライラしやすくなる人もいますが、産後10日ほどで自然に落ち着きます。[1]
一方で、産後うつはもう少し深刻な状態が続きます。
抑うつ気分や無気力が2週間以上続き、赤ちゃんをかわいいと思えなくなることも。家事や育児が手につかず自分を責めてしまうママもいます。
このような状態が続くと、日常生活に支障が出てきます。産後うつは「気の持ちよう」や「性格の問題」ではありません。場合によっては、医療機関での治療が必要です。
産後うつの症状とは
産後うつにはさまざまな症状があります。主なものを紹介します。
- 理由もなく涙が出る
- 常にイライラしてしまう
- 赤ちゃんをかわいく思えない
- 何もしたくない
- 食欲がない
- 眠れない
- 自分はダメな母親だと感じる
- 「消えてしまいたい」と考えてしまう
もし、こうした症状が2週間以上続いているのなら、ひとりで抱えこまずに誰かに相談してみましょう。
産後うつかもと感じたらどうしたらいい?5つの対処法
「産後うつかもしれないけれど、どうしたらいいか分からない」そう思ったら、今の自分にできる小さなことから始めるのがおすすめです。
ここでは今すぐできる対処法を5つ紹介します。
今の気持ちを誰かに話す
話すことで、心の中のモヤモヤが少しずつほぐれていきます。
パパや友人、地域の保健師さん、オンラインの知り合いなど、話を聞いてくれる人なら誰でも構いません。
専門家に話を聞いてほしいときはファミタスのオンラインカウンセリングも検討してみましょう。
5分でも自分の時間を作る
赤ちゃん中心の生活では、自分のことは後回しになりがちです。ほんの5分でも「自分だけの時間」があると気持ちがリセットされますよ。
何をしたらいいか分からないときは、次のことを試してみませんか。
- 好きな飲み物を味わう
- 好きな音楽を聴く
- 空を眺めて深呼吸する
- ストレッチする
忙しい日々の中で、自分を大切にするひとときも重要です。
家族や周囲に協力を頼む
「家のことは全部私がやらなきゃ」と思い込んでいませんか。無理だなと感じる前に、誰かに頼っていいんです。
- 掃除や洗濯はパパに任せる
- 実家や義両親にヘルプをお願いする
- 宅配食や家事代行を活用する
- 食洗器や自動掃除機を使う
ママが倒れないことは、赤ちゃんや家族にとっても大切です。周囲を頼ることは家族を守ることにもつながりますよ。
家事を頑張りすぎない
「部屋が散らかっている」「ごはんが手抜き」そんなふうに自分を責めなくて大丈夫です。
赤ちゃんのお世話は想像以上に手間や時間がかかります。産後の疲れた体が回復する前に赤ちゃんのお世話が始まるので大変ですよね。
「掃除の回数を減らす」「冷凍食品の活用」など、やらない家事を決めることも心の負担を減らすコツですよ。
眠る時間を確保する
睡眠不足は心と体の大敵です。赤ちゃんが眠っている間に「家事をしなくては」と無理をする必要はありません。その時間を使ってママも休憩を取りましょう。
授乳で夜にまとまって眠れない時期は昼寝も大切です。保育園やベビーシッターの活用なども効果的です。ママが元気に過ごせる方法を選んでくださいね。
「産後うつかも、どうしたらいい?」と悩むママの相談先
パパや友達、家族など周囲に相談しても気持ちが晴れるとは限りません。困ったときは専門家に相談してみましょう。
児童館や子育てセンター、自治体の相談窓口などがおすすめです。出産した産婦人科やかかりつけの小児科医もあなたの話を聞いてくれますよ。
具体的な相談先や相談方法については、関連記事を参考にしてくださいね。
関連記事:子育てで悩んだら?病院や自治体など頼れるサポート相談窓口5選
産後うつかもと感じたら誰かに相談してみよう
「産後うつかも。どうしたらいい?」と感じたら、パパや家族、友達など身近な人に相談してみるのがおすすめです。
「自治体の相談窓口や病院への相談は難しい」と感じている人は、ファミタスが運営するコミュニティや専門家によるオンラインカウンセリングも活用してみてくださいね。
参考文献
[1]公益社団法人日本産婦人科医会