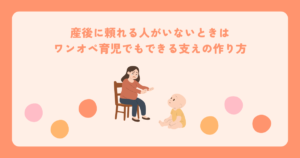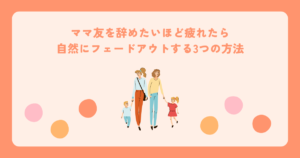前回の記事では、「自律神経」の働きについて解説しました。この記事では自律神経を整える効果が期待できる方法について詳しく解説します。
自分の時間を作るのが難しい子育て中でも簡単にできる方法です。無理せず、自分のペースで少しずつ取り組んでいきましょう。
自律神経を整える方法① 規則正しい入眠と起床
自律神経は、交感神経と副交感神経がうまく切り替わるようにすることで整えられるといわれています。
お金や時間をかけずにまず始められる方法が、生活リズムを整えることです。
参照:独立行政法人環境再生保全機構「Q7-4 自律神経にはどのような種類があり、どのような働きをしているのですか?」
朝日を浴びる
まずは朝起きたらカーテンを開けて、朝日を浴びましょう。朝の強い日の光を浴びることで体内時計はリセットされるといわれています。
睡眠と覚醒のリズムが整えられると朝の眠気が和らぎ、爽やかに目覚められるでしょう。
さらに日中に太陽光を多く浴びると夜間のメラトニンと呼ばれる睡眠を促す物質の分泌量が増加し、体内時計が調節されるため、自律神経を整える効果も期待されます。
育児中では、夜間の授乳や夜泣きであまり寝られず、朝に寝だめしてしまう方もいるかもしれません。
しかし、寝溜めして睡眠を取り戻すよりも、朝に一旦覚醒してしまい、赤ちゃんと一緒に少しの時間だけお昼寝する、あるいは夜早く寝るという生活の方が、体内の生活リズムは整いやすくなり自律神経を乱さずにすみます。

参照:良い睡眠の概要(案)(第2回健康づくりのための睡眠指針の改訂に関する検討会 参考資料3)
規則正しい睡眠習慣
交感神経と副交感神経のバランスを整えるためには、睡眠の習慣も重要です。
人は就寝2時間ほど前から睡眠を促すホルモンであるメラトニンの分泌が始まります。そのため、その時間帯に強い光の照明やスマートフォンのブルーライトの光を浴びてしまうと、メラトニンの分泌が抑制されて入眠が妨げられるということが報告されています。睡眠・覚醒リズムが遅れてしまい、夜は寝られず朝は起きにくくなった末に自律神経系が乱れていきます。
そのため、寝る前にはスマホ、タブレット、パソコンを見ないようにしたり、照明の照度を落としたり、睡眠のための環境を整えるのが大切です。
例えば、夜中の授乳やおむつ交換には目に強い刺激を与えにくい間接照明を使うと良いでしょう。また、子どもが寝たあとにゆっくりと映画を見たりスマホを見たりしたいという方は、メラトニンの分泌を抑制するといわれているブルーライトをカットできる眼鏡を活用すれば入眠を妨げなくなるかもしれません。
参照:良い睡眠の概要(案)(第2回健康づくりのための睡眠指針の改訂に関する検討会 参考資料3)
夜寝れなかったら短い昼寝を
乳幼児の子育て中は、自分のペースで睡眠を取ることができません。子どもの授乳や夜泣きで、1日眠れなかったということもあるでしょう。
夜寝られなかった分、朝たくさん寝ておこう、昼間にたっぷり寝ておこうとすると昼夜逆転の生活リズムになってしまう場合があります。
そのため、夜眠れず日中に強い眠気を感じるという場合には、昼寝を活用しましょう。昼寝といっても長時間寝るのではなく15~30分程度で構いません。これだけの短い昼寝でも日中の眠気を解消でき、午後もすっきりと過ごせます。
子どもがお昼寝をしているときに一緒に短時間の昼寝を取り入れると良いでしょう。
自律神経を整える方法②リラックスできる時間を作る
自律神経が乱れる理由の1つにストレスがあります。そのため、自律神経を整えるためにはリラックスできる時間を作ることも必要です。
さまざまなリラックス方法がありますが、ここでは自律神経を整える効果が期待できるリラックス方法について紹介します。
入浴
入浴をすると心身ともにリラックスできるという方も多いかもしれません。自律神経を整えたいという目的も兼ねて入浴する場合には、午前中や午後の早い時間の入浴ではなく、リラックスしやすい夕方あるいは夜の入浴が効果的といえるでしょう。
38度程度のぬるめのお湯に入るなら25~30分、42度程度の熱めのお湯が好みなら5分程度の入浴でリラックス効果が期待できます。
また約40度のお湯で30分ほど汗をかく程度の半身浴でも自律神経を整える効果が期待できます。子どもがいるとゆっくり入浴するのも難しいかもしれませんが、パパが休みの日は子どもの入浴をパパにお願いして1人の入浴タイムを楽しむのもよいでしょう。
このときに好きな香りのオイルや入浴剤で楽しむのもリラックス効果を高められる場合があるでしょう。
子どもがまだ小さいので、部屋の中でアロマオイルを使ったりアロマキャンドルを焚くのを諦めているという方も、お風呂に入れるのであれば、香りを無理なく楽しめるでしょう。

適度な運動
ウォーキングやジョギングといった有酸素運動は自律神経を整えることが期待できるため、実践してみましょう。
自律神経を整えるための適度な運動は週1回よりも複数回行う方がより効果的といわれています。
家事のみでは、自律神経が整うほどの活動量が期待できないので、子どもとのお散歩やお買い物の道中にベビーカーを押しながら少し早めに歩くなどして無理なく運動習慣を作ってみても良いでしょう。
参照:良い睡眠の概要(案)(第2回健康づくりのための睡眠指針の改訂に関する検討会 参考資料3)
ストレッチ
血流が悪くなるのも自律神経に影響を与えるとされています。そのため、ストレッチをして筋肉をほぐしたり、血流をよくしたりするのも自律神経を整える効果が期待できます。
ストレッチというと「時間を作らなきゃ」と身構えてしまうかもしれませんが、わざわざ時間を作る必要はありません。
肩や首をゆっくりと回したり、首を曲げ、曲げたほうの手で首を伸ばしたり、腕をまっすぐ伸ばして反対の手で伸ばしたりするだけでも構いません。
できる範囲で無理なく行いましょう。
参照:自律神経を整えるには。セルフケアを始めよう(大正健康ナビ)
自律神経の整え方③ストレスをためない
ストレスは自律神経が乱れる原因です。
好きなことをしてストレスを解消するのが良いですが、子育て中に自分の時間を作るのは難しいでしょう。
身近な人に育児を頼める方は頼んでストレス解消の時間を作ったり、あるいは市町村の一時預かりをして自分の時間を確保したりして、リフレッシュすると良いでしょう。

まとめ
自律神経を整えるためにわざわざ時間を作らなくても、日々の生活の中に自律神経を整える効果が期待できる行動のヒントが散らばっています。
特に乳幼児を育てるママは自分の時間をなかなか取れません。
しかし、自律神経を整えれば疲労感や睡眠不足、睡眠不足による精神的な不安感などのママ自身の体や心の悩みも軽減しやすくなり、子どもに向き合う余裕もでてくるのではないでしょうか。
無理に時間を作らずできることから気軽に試してみると、自分にぴったりの方法が見つかるかもしれません。