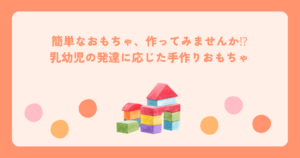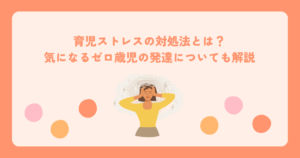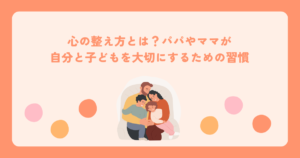私には、4歳の一人娘がいます。
診断名はついていないものの、いわゆる発達のグレーゾーンにいる子です。
そんな娘は、2歳8カ月で療育に通い始めました。
ここでは、娘が療育を受けるに至った経緯や、親の気持ち、療育を受けてどう変わったかについて述べたいと思います。
療育を勧められるまでの娘の様子
生まれてから1歳半を過ぎるまで
娘は、妊娠中も生まれてからも大きな病気やけがをすることなく、元気にすくすく育ちました。
2カ月でクーイングが出て、3カ月で首が座り、7カ月でつかまり立ちできるようになり、1歳の誕生日を迎える前には、1人で歩けるようになりました。
成長を日々感じる一方で、1歳半を迎えても「あ」や「うー」などをごくまれに言うだけで、意味のある発語が出る気配すらありませんでした。
他にも、絵本で「〇〇はどれ?」と聞いても指さしをせず、積み木は積まずに並べ、逆さバイバイをするなど、月日とともに気になる点が増えていきました。

1歳半健診で指摘あり
そして迎えた1歳半健診。
当時は自宅保育だったため、同じ会場で健診を待っている他の子の様子を見て、「もうそんなに話せるの?」「そんなに指示が通るの?」と驚いたことを今でも覚えています。
肝心の健診結果は、やはり意味のある発語なし、指さしなし、積み木を積まないことを指摘されました。
そのため、2カ月後にある再検査と市が主催する言葉の教室を紹介されました。
そして、再検査当日。
指さしは何とかできるようになったものの、積み木遊びの指示は通らず、意味のある発語も相変わらずないことから、遊びを通して発語を促しつつ「2歳まで様子を見ましょう」とのことでした。
2歳を過ぎても様子は変わらず
2歳の誕生日を迎えても、娘はたまに単語らしきものが出る程度でした。
そして、2回目の言葉の教室に参加した際に、担当の言語聴覚士の先生から療育も視野に入れるように勧められました。
2歳を過ぎて活発さが目立ち、言葉の教室でも椅子に座って先生のお話を聞けなかったこともそう言われた要因の一つだと今では思います。
療育の目的はあくまでママ以外から刺激を受けることであり、いろいろな考え方があるから、療育に行くか行かないかは親の判断に任せるとのことでした。
私は、娘の成長につながるならと思い、その場で療育を受けたい旨を伝えました。
療育に対する親の気持ち
自分を責める気持ち
療育が必要だといわれて、真っ先に思ったことは「私のせいかな」でした。
転勤族のため見知らぬ土地で子育てをしており、支援センターもコロナ渦で利用が制限され、ずっと自宅保育をしていました。
夫は娘が寝てから帰宅することも多く、娘が接する大人はほぼ私だけ。
そのため、自分の接し方が悪かったのか、絵本の読み聞かせの量が少なかったのか、栄養たっぷりのご飯じゃなかったからかなど、さまざまな憶測で自分を責めました。
どこかホッとした気持ち
その一方で、「私の考えすぎではなかったんだ」と安心したのも事実です。
夫や実家の家族は、「まだ小さいんだからこういうものだよ」「気にしすぎじゃない?」という考え方だったので、第三者かつ専門家がそう判断するのなら、私の直感は間違ってなかったんだと思えました。
前向きな気持ち
自分を責める気持ちと、ホッとした気持ちの繰り返しの中で行きついたのは、前向きな感情でした。
家庭以外に居場所ができて、専門家による特性に応じた支援が受けられることは、娘にとっても親にとっても心強いことだと思えたのです。
発達の遅れが気になると毎日モヤモヤして過ごすよりも、せっかく療育というサポートがあるのだから利用しない手はない、と前を向くことができました。
療育に通ってからの娘の変化
人見知りがなくなった
療育の効果は、通い始めてすぐに感じました。
それまで、公園に行っても母親から離れず、同世代の子を見るとギャン泣きしていた娘が、公園で親を放って1人で遊べるようになったのです。
それまで常にママと2人きりだったので、療育を通して娘の世界が広がったのだと感じました。
言葉が少しずつ出てきた
一番心配していた言葉の面では、徐々に成長が見られました。
まず、私が話している時に、私の口元をよく見るようになりました。
そして、私の発音をまねしたり、頑張って何か言葉を発そうとする姿をよく見るようになりました。
「(いないいない)ば!」「おいいい(おいしい)」など、言葉での意思疎通が取れるようになり始めました。
感情が豊かになった
そして、一番変わったなと思ったのは、感情表現が豊かになったことです。
もちろん、療育に通う前も笑ったり、泣いたり、怒ったり、喜んだりしていました。
しかし、嬉しいときは「ったー(やったー)」とジャンプをしたり、笑うときもほとんど微笑むだけだったのが「あはは」と声を出して笑ったり、怒るとぷいっと私を無視したりと、娘の思っていることがより分かりやすくなりました。

療育を始めてからの親の変化
親が一人で抱え込まなくなった
療育は、子どもだけではなく、親にとっても心強い存在となりました。
ちょっとした相談にも、先生方が的確なアドバイスをくれるからです。
くよくよ悩みがちな私にとって、いつでも相談できる相手がいるというだけで気持ちが楽になりました。
娘への接し方を学べた
療育先では、娘への接し方に関するアドバイスをたくさんもらえました。
かんしゃくを起こしたらは、安全を確保して本人の気持ちが落ち着くまで待つこと。
どんな些細なことでもたくさん褒めること。
見通しを持たせた声掛けをすること。
絵カードですべきことを可視化する、などです。
娘が過ごしやすい環境を意識することで、娘のかんしゃくも減り、親も慌てずに対応できるようになりました。
リフレッシュの時間が確保できた
また、娘の成長以外にも、うれしいことがありました。
娘が母子分離の療育に行くことで、私の一人時間ができたのです。
当時は夫も仕事が忙しく、私のリフレッシュ時間はほぼゼロでした。
そのため、私の自由時間が確保できたことで、心に余裕が生まれ、娘がよりかわいく思えるようになりました。
まとめ
娘の発達が気になりだすまで、私は療育という言葉すら知りませんでした。
きっと娘が何の心配もなく育っていたら、出会えなかった人や考え方があるなと今では思います。
療育に通うと著しい成長が見られる、とは思っていません。
しかし、私たち家族は療育に通わせてよかったなと日々実感しています。
これからも周囲の手を借りながら、のんびり成長していく娘を見守っていこうと思っています。