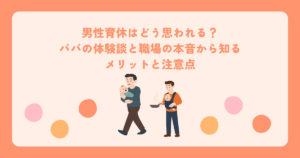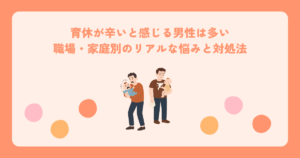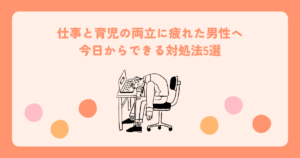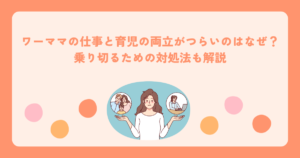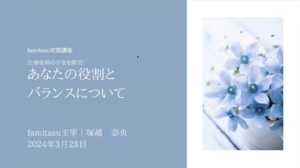出産後のママは不安や孤独を感じやすく、パパ自身も仕事と育児の両立でストレスを抱えやすくなっています。
夫婦で協力して育児に取り組むために活用できるのが「パパママ育休プラス」です。
パパママ育休プラスにより、育休を取得できる期間を延ばせるだけでなく、夫婦のこころの健康を守る助けにもなります。
この記事では制度の概要とあわせて、産後うつの予防や夫婦のメンタルケアとの関連も解説します。
パパママ育休プラスとは
パパママ育休プラスとは、パパとママが順番に育休を取得することで、子どもが1歳2か月になるまで育休期間を延長できる制度です。[1]
共働き世帯が増える中で、ママだけが育休を取得するケースでは心身への負担が偏りやすい現状があります。
そこで、夫婦で協力して育休を取りやすくするために、パパママ育休プラスが設計されました。
パパママ育休プラスは、ママだけでなくパパの心身の負担を軽くし、赤ちゃんとの時間を家族で大切にできるように考えられた制度です。
制度を理解しておくことで、自分たち夫婦に合った育休のかたちを安心して選べるでしょう。
パパママ育休プラスと「産後パパ育休」の違い
パパママ育休プラスと産後パパ育休の違いは以下のとおりです。
■産後パパ育休
赤ちゃんの出生後8週間以内に、最大4週間までパパが育休を取得できる制度です。
2回に分けての取得も可能で、出産直後のママや赤ちゃんをサポートすることを目的としています。[2]
■パパママ育休プラス
両親がともに育休を取得することで、通常1歳までの育休を「1歳2か月まで」に延長できる制度です。
出産直後だけでなく、その後の子育てを長期的に分担するための仕組みです。
パパママ育休プラスは育休期間を延ばして夫婦で子育てを分担する制度であり、産後パパ育休は出産直後のサポートと整理するとわかりやすいでしょう。
パパママ育休プラスを利用するメリット
パパママ育休プラスを利用するメリットとして、以下が挙げられます。
■家事や育児の分担ができる
夜間のミルクやオムツ替えを夫婦で行うことによりママの負担が軽くなる
■夫婦で子育ての時間を共有できる
育児の喜びや大変さを夫婦で共有することでママの安心感につながる
■赤ちゃんと過ごせる時間が増える
パパが育児に関わる時間が増えることで父子の愛着形成が進み、赤ちゃんの情緒の安定にもよい影響がある
パパが育休を取ることで家事や育児を分担でき、ママは休養の時間を確保しやすくなります。
パパママ育休プラスは、育休が取得できる期間を延ばせる制度であると同時に、ママのこころのケアや夫婦関係、赤ちゃんの成長にとっても大きな意味を持つ制度といえるでしょう。
男性の育休中や復帰後の悩みについて知りたい方は、こちらの記事を合わせてご覧ください。
育休とメンタルヘルスの関係
育休の取得は、パパやママのメンタルヘルスを守るうえでも大切な役割を果たします。
たとえば、育休取得率の高いヨーロッパ諸国では、男性の産後うつの割合が低い傾向が示されています。[3]
これは育休取得により、産後のパパの精神的なストレスが軽減されている可能性があると考えられているのです。
また、パパが育休を取得することで、ママの抑うつ症状を改善する方向に働くこともわかっています。[4]
パパの育休はパパ自身のメンタルヘルスを守るだけでなく、ママの産後うつリスクを下げる効果も期待できるのです。
育休は夫婦で子育てを分担し、こころの健康を守るための重要な仕組みといえるでしょう。
パパの産後のメンタルヘルスについて詳しく知りたいときは、以下の記事を合わせてご覧ください。
パタニティブルーとは|セルフチェックと夫婦で乗り越えるためにできること
産後うつの予防のためにパパママ育休プラスを利用しよう
パパママ育休プラスは、育休を延ばせる制度であると同時に、パパとママのメンタルヘルスを守る仕組みです。
出産後のママは、ホルモンの変化や睡眠不足、孤立感からこころが不安定になりやすく、産後うつのリスクが高まります。
また、産後はパパも育児と仕事の板挟みでストレスを抱え、メンタルが不安定になりやすい時期です。
パパの育休所得はママの負担を減らすだけでなく、パパ自身も育児に主体的に関わる機会が増え、精神的な充実感につながります。
パパママ育休プラスは育児するママを支えるための制度でありながら、夫婦それぞれのこころの健康を守る制度でもあります。
制度を活用して家族全員が安心して子育てできる環境を整えることが、産後うつの予防にもつながるでしょう。
制度をどう活用するか、夫婦でどう話し合えばよいかは迷いや不安があるときは、famitasuのオンラインカウンセリングをお気軽にご利用ください。
参考資料
[1]厚生労働省
パパ・ママ育休プラス
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/var/rev0/0146/0019/papamama.pdf
[2]厚生労働省
産後パパ育休
https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/content/contents/001853014.pdf
[3]日本小児科学会
男性の産後うつと育児休業に関するアンケート調査
https://www.jpeds.or.jp/uploads/files/20230309_seiikukihonhou_houkoku.pdf
[4]今西洋介
男性の産後うつと育児休業
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jrsj/42/4/42_42_324/_pdf