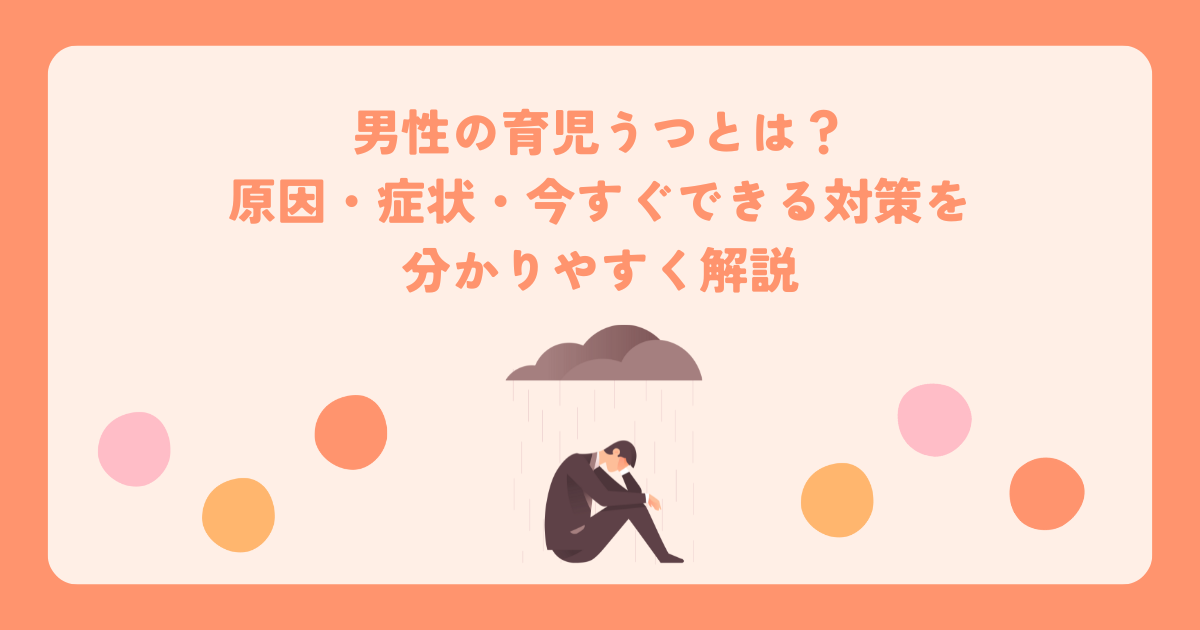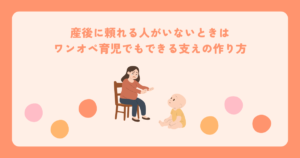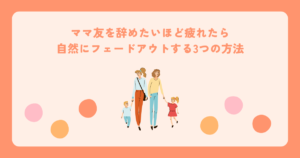「赤ちゃんが生まれて幸せなはずなのに、なぜか気分が沈む」「仕事と赤ちゃんのお世話に追われて、些細なことでイライラする」そう感じているパパは、もしかすると育児うつかもしれません。
本記事では、男性の育児うつの原因や症状、そして今日から始められる対策について分かりやすく解説します。
男性の育児うつとは
男性の育児うつとは、赤ちゃんが生まれた後にパパの心にあらわれる不調を指します。
「産後うつ」という言葉はママの症状を指すことが多いですが、医学的にはパパにも起こりうる心の病気です。「父親の産後うつ」と呼ばれることもありますが、一般向けに「育児うつ」と表現されることもあります。
国の研究班が実施した調査では、およそ10人に1人のパパが育児期にうつ症状を経験していると判明しました。これはママの産後うつとほぼ同じ割合です。[1]
2024年、国立成育医療研究センターが自治体向けに産後うつの父親を支援するためのマニュアルを作成しました。今後パパの育児うつ支援に取り組む自治体は増加するでしょう。[2]
育児うつになりやすいパパの生活やセルフチェック方法については、こちらの記事をご覧ください。
男性の育児うつの原因
パパが育児うつになるにはいくつかの原因があります。ここでは、主なものを5つ見ていきましょう。
生活リズムの激変による睡眠不足
産後は赤ちゃんの夜泣きや授乳対応で睡眠が細切れになり、慢性的な寝不足が続きます。元々長時間労働で睡眠不足気味の場合、さらなる疲労が蓄積されるでしょう。睡眠不足は感情のコントロールを難しくし、気分の落ち込みやイライラを引き起こします。
仕事と育児の板挟み
職場と家庭、両方の責任を果たそうと、無理をしてしまうパパは少なくありません。しかし、どちらも中途半端にしかできないと感じ、自己否定に発展するケースがあります。
理想の父親像と現実のギャップ
「頼れるパパになりたい」「仕事も育児も完ぺきにこなしたい」という理想や固定観念を抱くパパもいるでしょう。理想と実際の育児との間にギャップを感じ、自己否定感につながることがあります。
孤独感やサポート不足
「困っていることを知られたくない」と考えるパパは、友人や同僚に気軽に相談できずに1人で抱えがちです。ママも育児に追われていると、家庭内でも弱音を吐けないこともあるでしょう。育休を取って職場と切り離されることに不安を感じるパパもいます。
今までパパの育児うつはあまり研究されていませんでした。国の研究や行政サポートも始まったばかりです。
このような孤独感や支援不足も心の不調を悪化させる要因です。
パートナーの不調による影響
ママが産後うつになった場合、パパの育児うつの発症率も大きくアップすると言われています。これは、ママのサポートをするために、自分を後回しにして育児や家事を行い疲労が蓄積するだけでなく、精神的にも負担が増えるためです。
男性の育児うつによくある症状
パパの育児うつについて、主なものを3つ紹介します。ここで紹介する以外にも、家族や仕事への興味の減退、食欲不振・倦怠感などの身体症状があらわれることもあります。
このような症状が続き、日常生活に支障が出る場合は早めに医療機関を受診しましょう。
気分の落ち込みや憂うつ感
何をしても楽しくない、気持ちが重いと感じ、朝起きるのがつらい状態が続きます。
怒りっぽくなりイライラが増える
些細なことで感情的になることがあります。また、感情をコントロールできず部下や家族にきつく当たってしまうこともあるでしょう。
集中力や判断力の低下
仕事や家事の効率が落ち、ミスや忘れ物が増えます。活字が頭にスムーズに入ってこなくなりパフォーマンスが落ちることもあります。
今すぐできる男性の育児うつ対策
今すぐできる育児うつ対策を3つ紹介します。できそうなものから1つずつ取り入れてみてはいかがでしょうか。
睡眠と休養を優先する
睡眠不足や過労は育児うつの大きな要因の一つです。短時間でも横になる、昼寝を取り入れるなど、意識的に体を休めましょう。
家事・育児の分担を見直す
パートナーや家族と話し合い、無理のない分担に調整しましょう。家電や総菜の活用、ベビーシッターや家事代行の利用なども効果的です。負担が軽減すれば、気持ちも軽くなります。
信頼できる人や専門家に相談する
友人、同僚、親など、安心して話せる相手に思いを打ち明けることが回復のきっかけになります。症状が続く場合は、心療内科やカウンセラーに早めに相談しましょう。
男性の育児うつは早めの気づきと対策が大切
パパの育児うつは10人に1人と言われており、決して珍しいことではありません。心の不調も風邪と同じように、早めのケアが回復への近道です。
「おかしいな」と感じたら1人で抱え込まず、早めに信頼できる人や専門機関へ相談しましょう。
参考文献
[1]NHK│父親も「産後うつ」に 国の研究班が支援マニュアルを作成
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250119/k10014697201000.html
[2]国立研究開発法人国立成育医療研究センター│自治体向け父親支援マニュアル【2024年度】
https://www.ncchd.go.jp/scholar/research/section/policy/project/2024_manual.html