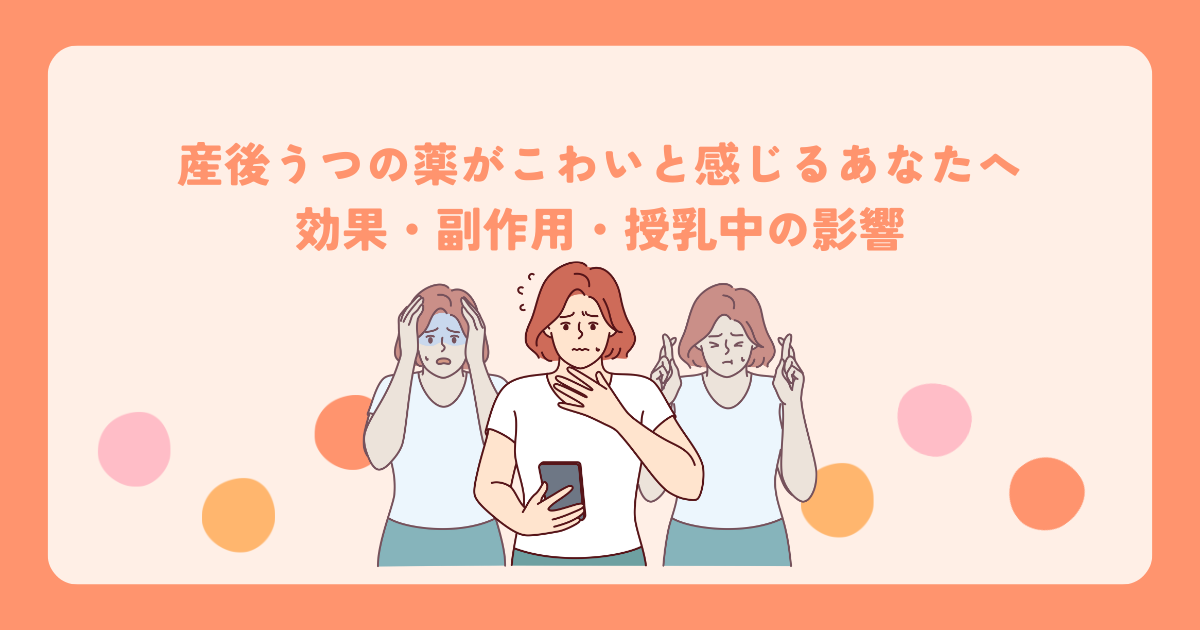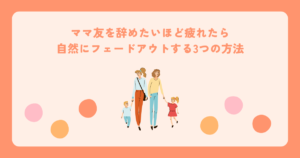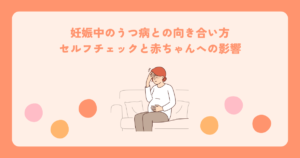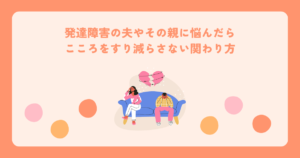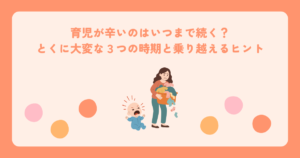産後うつと診断され薬の服用を勧められても「副作用はないの?」「授乳中でも大丈夫なの?」と不安を感じてしまうのではないでしょうか。
この記事では、産後うつの薬に関する効果や副作用、授乳への影響などについて解説します。
どうしても薬への抵抗があるときには、この記事を参考に漢方薬やカウンセリングなどの選択肢を検討してみてください。
薬を使うかどうか迷っているあなたが、納得のいく選択ができるよう参考になれば幸いです。
産後うつで薬を使うのは自然な選択肢
精神科で薬を勧められると「薬を飲むと人格が変わってしまうかも」「もとの自分に戻れなくなってしまうかも」という不安や恐怖を感じるかもしれません。
ただ、産後うつにおける治療の原則は「休息」と「抗うつ薬」であり、産後うつで薬を使うのは、自然な選択肢のひとつです。[1]
抗うつ薬は、もともと持っているセロトニンやノルアドレナリンなどの働きを助け、こころのバランスを取り戻す役割を持っています。[2]
薬を使うかどうかは医師と相談しながら自分で決められるため、不安や迷いがあれば医師に伝え、あなた自身が納得する選択をしましょう。
産後うつの症状やなりやすい人の特徴などについて詳しく知りたい方は、こちらの記事を合わせてご覧ください。
産後うつで使われる薬と効果が出るまでの期間
産後うつでおもに使われるのは、気分を安定させる「抗うつ薬」です。
なかでも副作用が少ないとされる「SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)」や「SNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)」という薬がよく処方されています。
ただ、抗うつ薬は飲んですぐに効果が出るものではありません。
2週間前後かけて少しずつ効いてくるという特徴があるため、本当に効くのかな?と不安になったときは、焦らず医師と相談しながら服用を続けることが大切です。[2]
不安や不眠が強いときには、抗不安薬や睡眠導入剤などを併用することもあります。
これらの薬は抗うつ薬と比べると効果を実感できるのが早いため、少しだけでも気持ちを落ちつけて休みたいときに頼れるお薬です。
産後うつの薬による副作用
現在よく使われている抗うつ薬(SSRIやSNRIなど)は副作用が少ないとされていますが、以下のような症状を感じることがあります。
- 眠気
- だるさ
- 口の渇き
- 吐き気
- 胃のムカつき
このような副作用は飲み始めて1週間前後に出やすいとされていますが、多くは時間の経過とともに落ち着いていく傾向があります。[2]
副作用が強くて育児がつらくなってしまうときは、薬の種類を変える・量を減らすなどにより身体への負担を減らせるため、遠慮せず医師に相談しましょう。
産後うつの薬は授乳中でも服用できるものがある
抗うつ薬のなかには、授乳中でも使えるものがあります。
たとえば、代表的な抗うつ薬であるSSRIは、母乳に移行する量がごくわずかで、赤ちゃんへの影響も少ないとされています。[3]
赤ちゃんへの影響を心配しすぎて治療を開始せず、つらさを抱えた状態で育児を続けるとママのこころと身体がすり減ってしまうでしょう。
抗うつ薬をうまく取り入れてママ自身が穏やかに過ごせることは、赤ちゃんとの関係にもよい影響を与えます。
授乳や薬について不安が大きいときは、ムリに我慢せず主治医に正直な気持ちを伝えてください。
母乳育児をやめると子どもへの影響が心配という方は、こちらの記事をご覧ください。
漢方薬やカウンセリングという選択も
どうしても抗うつ薬を飲むことに抵抗があるときは、医師に薬以外の治療法はないか相談しましょう。
症状の程度によっては、以下のような方法が検討できます。
- 漢方薬の服用
- カウンセリング
- 生活環境の見直し(例:家事や育児の負担軽減)
大切なのは「薬を使う・使わない」ではなく、あなたが安心して治療に取り組める選択をすることです。
不安や迷いを感じていることも、治療を進めるうえで大切な情報です。気になることがあれば、ためらわず医師や看護師に相談しましょう。
産後うつの診断を受けた方の体験談や子どもへの影響などが知りたいときは、こちらの記事をご覧ください。
産後うつの薬に対する不安や迷いは相談しよう
子育てをしながら産後うつの薬を使うことに、不安や迷いを感じるのはとても自然な気持ちです。
ただ、産後うつで使われる抗うつ薬は副作用が少なく、授乳中の方も使いやすいとされています。
薬の効果や副作用、授乳への影響など、気になる点があるときはひとりで抱え込まず、医師や看護師に正直な気持ちを伝えましょう。
ご自身が納得して治療に取り組み、安心して回復に向かえる選択をするのが何よりも大切です。
参考資料
[1]妊産婦のメンタルヘルスの基礎知識
うつ病(産後うつ病・周産期うつ病)
https://boshikenshu.cfa.go.jp/assets/files/history/r5/tr1_lecture_1.pdf
[2]こころの耳
薬物療法
https://kokoro.mhlw.go.jp/about-depression/ad003
[3]日本産婦人科医会
妊産婦メンタルヘルスケアマニュアル P49
https://www.jaog.or.jp/wp/wp-content/uploads/2018/03/mentalhealth2907_L.pdf