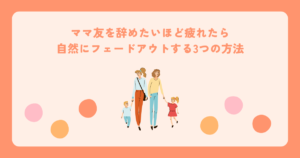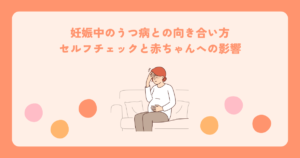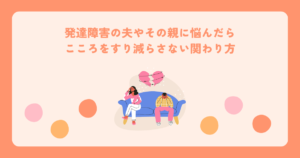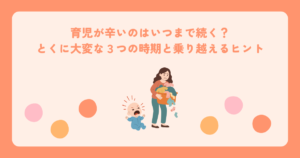出産後のママは、ホルモンバランスの変化や育児の忙しさで、心も体も大きくゆらぎやすい時期です。
実は、ママだけではなくパパも産後うつになることがあるって知っていましたか?[1]
産後うつは誰にでも起こりうるもの。だからこそ、ママもパパも産後うつのサインを知って「もしかして?」と気づけるようにしておくことが大切なんですよ。
この記事では、産後うつになりやすい人の特徴、早めに気づくためのサイン、対策方法についてわかりやすく解説します。
産後うつとは
産後うつは、出産後にママやパパの心に現れる不調から始まります。
育児のプレッシャーや生活の変化、体調の変動などが重なり、気分が落ち込んだりやる気が出なかったりする状態です。
多くの場合、2週間以上症状が続き、日常生活に支障が出る状況になると産後うつと診断されるようです。ただし、人によって異なりますので不安な場合は早めに医療機関を受診してみましょう。
ママの場合は、出産によるホルモンバランスの大きな変化も一因です。パパの場合、環境の変化やプレッシャーから産後うつになることがあるんですよ。
研究によると、産後うつになるママ、パパはおよそ1割程度と言われています。[2]
特に、産後数週間から数か月の間は誰でも心が揺らぎやすい時期です。「疲れているだけ」と思い込まずに、心の変化にも目を向けてみましょう。
【ママ・パパ共通】産後うつになりやすい人の特徴
産後うつになりやすい人の特徴を見ていきましょう。
ここに当てはまる人が必ず産後うつになるわけではありません。しかし、傾向を知っているだけでも早めの対策につながりますよ。
真面目で責任感が強い
「私がしっかりしないと」と思うあまり、自分を追い込んでしまうタイプの人は注意が必要です。 育児は思い通りにいかないことも多いので、頑張りすぎないことが大切ですよ。
周りに頼るのが苦手
「私が頑張ればいい」と思い込み、一人で抱え込んでしまう人も心の疲れがたまりやすくなります。
環境の変化に弱くストレスを感じやすい
産後は赤ちゃん中心の生活となり、生活リズムが乱れがちです。育休を取る人や他のママ・パパとの交流が増え、人間関係が変化する人も。こうした変化が苦手な人は、無意識のうちにストレスを抱え込むことがあります。
これまでに心の不調を経験したことがある
過去にうつ病など心の不調を経験した人は、出産や育児を機に再び心のバランスを崩しやすくなることがあります。
産後うつになりやすい人の特徴【ママの場合】
ママは産後、体力が回復しないうちに育児が始まります。そのため、思っている以上に負担を抱えていることも。次のようなサインはありませんか。
- 理由もなく涙が出る、気分が落ち込む
- 赤ちゃんのお世話に喜びを感じられない
- 極端な食欲の変化(食べすぎ・食欲不振)
- 自分を責める気持ちが強くなる
- 何もやる気が起きない
こんなときは、少し立ち止まり自分のケアも考えてみてくださいね。
産後うつになりやすい人の特徴【パパの場合】
パパの産後うつは、ママと少し違う現れ方をすることもあります。 パパの場合、こんなサインがないか気にかけてみてください。
- 家にいると落ち着かず、外に出たくなる
- イライラしたり怒りっぽくなったりする
- 仕事への集中力が落ちる、無気力になる
- 家族と距離をとりたくなる
長時間労働と赤ちゃんの育児が重なり産後うつになる人も。「パパだから頑張らなきゃ」と自分を責めすぎず、心がつらいときはしっかり休むことも必要です。
ママとパパのための産後うつ対策
産後うつを完全に防ぐのは難しいかもしれません。けれども、ちょっとした心がけで、リスクをぐっと減らせるので試してみてくださいね。
完璧を目指さない
赤ちゃんのお世話は、思い通りにいかなくて当たり前です。「うまくいかない日もあるよね」と、少し肩の力を抜いてみましょう。
小さな「助けて」を口にする
ひとりで育児をするのは想像以上に大変です。疲れたときやしんどいときは、家族や自治体など、周囲のサポートを上手に頼ってみてくださいね。
ママもパパもお互いの変化に気づく
ママとパパ、どちらかが少し元気がないときは、無理に励まさずそっと寄り添うだけでも支えになります。
必要なら専門家に相談を
「なんだかしんどいな」「このままだと苦しいかも」と感じたら、早めに医療機関や相談窓口にアクセスしましょう。 小さなサインに早く気づくことが、何より大切です。
ママもパパも産後うつの対策に取り組んでみて
産後はママもパパもこれまでにない環境のなかで頑張りすぎることがよくあります。産後うつは誰にでも起こりうるもの。自分を責める必要はありません。
産後うつを防ぐには、ちょっとした心の変化に気づき、「無理しない」「頼っていい」という気持ちを持つことが大切です。
ママもパパも無理をせず周りの力を借りながら子育てを進めていきましょう。
[1]国立研究開発法人 国立成育医療研究センター
https://www.ncchd.go.jp/scholar/research/section/policy/project/2024_manual.html
[2]国立研究開発法人 国立成育医療研究センター
https://www.ncchd.go.jp/scholar/assets/7a9c3db5c293e8016ca72df23efe9877.pdf