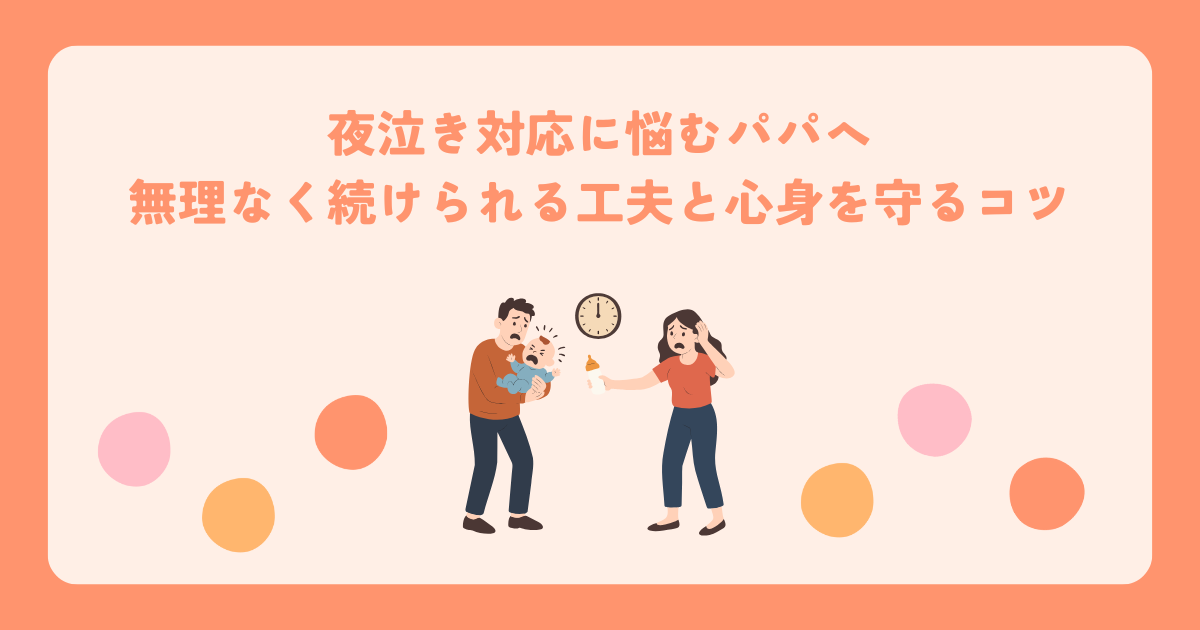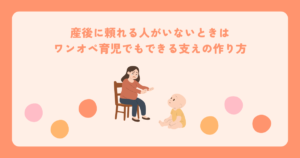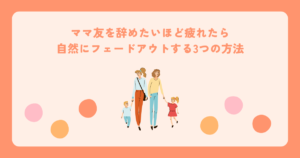赤ちゃんの夜泣きで寝不足が続き、仕事や生活に支障が出ていると感じていませんか。
「母親が大変なのは分かるけれど、自分もつらい」と悩む父親は少なくありません。
ひとりで悩むうちに自信をなくしたり、弱音を吐けず心身に影響が出てしまうこともあるでしょう。
この記事では、父親が夜泣き対応で感じるつらさや無理のない対応方法、心身を守る工夫などについて紹介します。
無理せずに取り入れられるヒントを知ることで、安心して夜を迎えられたら幸いです。
夜泣き対応で父親が感じるつらさ
夜泣きは母親だけでなく、父親にとっても大きな負担です。
父親は「仕事」と「育児・家事」を同時に担っているため、睡眠不足により以下のような支障をきたしやすくなります。
- 仕事中の集中力が落ちる
- 通勤中の運転が危険になる
- 弱音を吐けず精神的に追い詰められる
こうした影響を抱えながらも、父親たちは工夫を重ねて夜泣きに向き合っているのです。
実際に、夜泣きの対応として散歩や電動ゆりかごを試すなど、父親なりに工夫を重ねて育児に協力する様子が報告されています。[1]
父親が夜泣き対応でつらさを抱えるのは自然なことであり、そのつらさを認めることが家族全体の健やかな生活につながります。
仕事と育児で疲れてしまった男性の本音が知りたいときは、こちらの記事を合わせてご覧ください。
父親ができる夜泣き対応
父親が無理なくできる範囲で関わることが、家族の安心につながります。
具体的には、次のような工夫が役立つでしょう。
■交代制を取り入れる
平日・休日で役割を分ける、時間を区切って夫婦交代で対応するなどルールを決める
■できることから関わる
授乳後の寝かしつけを担当する、泣き始めを見守るなど母乳が必要な場面以外を担当する
このように夜泣きのすべてに対応する必要はありません。
国立生育医療センターによる研究では、できる範囲で父親が子どもに関わるほど、子どもの発達や夫婦関係の安定によい影響があると報告されています。[2]
「自分はうまくできていないのでは」と育児に自信を持てないときは、こちらの記事を合わせてご覧ください。
夜泣き対応をする父親が心身を守るための工夫
父親が夜泣き対応をするときは、自分の心身を守るための工夫が欠かせません。
実際に、夜泣きは父親の睡眠不足や疲労に直結することが明らかになっています。[3]
無理を続けると仕事だけでなく家庭全体が苦しい雰囲気になってしまうため、次のような工夫を取り入れて心身の負担を軽くしましょう。
■睡眠の質を高める
耳栓やアイマスクを使う/昼休みに短時間の仮眠を取る
■休めるときはしっかり休む
自分の担当時間外はゆっくり休む/眠れなくても目をつむって身体を休ませる
■体調がつらいときは相談する
過労や気分の落ち込みが強いときは医療機関や相談窓口に早めに頼る
自分を守る工夫は前向きに育児をするための大切な土台であり、父親自身が元気でいることが妻と子どもを支える力になります。
仕事と育児の両立に疲れたときの対処法は、こちらの記事でご確認いただけます。合わせてご覧ください。
夜泣き対応は父親と母親のコミュニケーションが不可欠
夜泣きは、夫婦どちらか一方が抱え込むとすれ違いや不満につながりやすいものです。
お互いの状況を共有しないまま夜泣き対応を続けると「なぜ自分ばかりが大変なのか」という気持ちが膨らみ、夫婦関係に悪影響を及ぼします。
父親の子育て参加に関する研究では、父親が家事や育児、母親とのコミュニケーションに関われば関わるほど夫婦関係がよくなり、母親のストレスが減ることが確認されています。[4]
たとえば、次のようなコミュニケーションを意識することで、夫婦で協力しやすくなるでしょう。
■責め合わない
お互いに無理なく続けられる形を見つけることを前提に話し合う
■役割を押しつけない
それぞれの得意・不得意や生活リズムを踏まえて分担する
■前向きな声かけを意識する
「ありがとう」「一緒に工夫してみよう」など、協力の姿勢が伝わる言葉を選ぶ
父親ができる範囲で関わり積極的なコミュニケーションを意識することは、子どもの安心感を育むだけでなく夫婦の絆を強める力にもなります。
夫婦のすれ違いを防ぐ方法が知りたいときは、こちらの記事を合わせてご覧ください。
まとめ
夜泣きは赤ちゃんの成長に伴う自然な現象ですが、父親にとっても睡眠不足や疲労をもたらし、仕事や家庭生活に影響を与えます。
研究でも父親が夜泣き対応で疲弊する姿や、仕事と家庭の両立で悩む様子が報告されており、あなたの悩みは決して特別なことではありません。
大切なのは、家族みんなが無理をせずできる範囲で育児を続けることです。
自分を守りながら夜泣きに向き合うことが、結果的に家族みんなの安心につながるでしょう。
心身の疲労がたまって誰かに話をしたいときは、famitasuのオンラインカウンセリングをお気軽にご利用ください。
参考資料
[1]岡田 麻代、松井 弘美、西村 香織、三加 るり子、北島 友香
育児を行っている父親が妊娠期から育児期を通して感じた困難な状況
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjam/39/1/39_JJAM-2024-0026/_pdf/-char/ja
[2]加藤承彦
父親の育児参加が母親、子ども、父親自身に与える影響に関する文献レビュー
https://www.ncchd.go.jp/scholar/assets/d5b6a3954692737ff798175682868a42.pdf
[3]出石 万希子、新小田 春美、武士 葉子、大林 陽子
生後4か月児をもつ父親の平日育児時間と疲労度からみた父子の睡眠リズムおよび育てにくさの実態
[4]尾形和男
父親の子育て参加と家族のウェルビーイング―家庭における父親の存在感