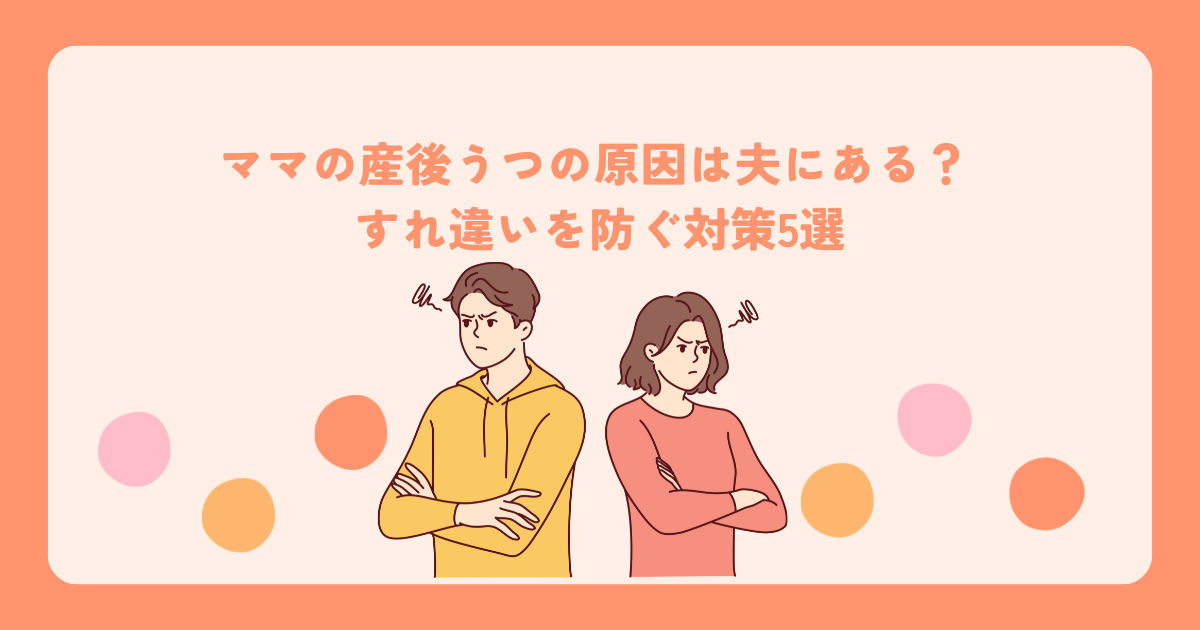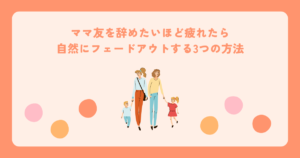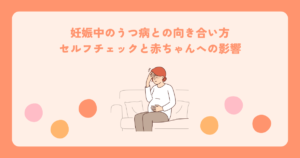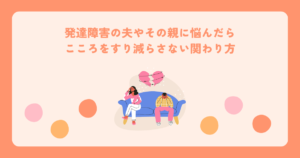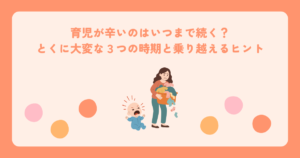出産後、ママの心と体は大きく変化します。初めての育児への戸惑いや責任感、夜泣きや授乳による睡眠不足、体の痛みやホルモンバランスの乱れなど、ママの負担は計り知れません。
そんな日々を過ごすなかで、「パパにイライラしてしまう」「なんでわかってくれないの?」と感じる人も多く見られます。
パパとのコミュニケーション不足やすれ違いが重なることが、産後うつの一因になることも。
この記事では、パパが知っておきたい産後うつの背景や夫婦のすれ違いを防ぐための5つの対策を紹介します。
夫が知っておきたい産後うつの原因とママの心の変化
産後のママに起きている変化は、目に見えるものばかりではありません。ホルモンバランスの急激な変化や寝不足、孤独感、育児へのプレッシャーなどが重なり、心が不安定になりやすい時期でもあります。
心が不安定になりやすい時期なので、「自分では気持ちをコントロールできない」「ささいなことで涙が出てしまう」というママも少なくありません。
産後うつになる背景の一つとして、ママの心にゆらぎがある時期にパパのサポートが不足することも挙げられています。[1]
パパが産後の変化について正しく理解すれば、ママの安心感はぐっと高まります。「産後は揺らぎやすい時期なんだな」と知っておくことが大切です。
産後うつの原因のひとつは夫婦のすれ違い
産後うつの原因はひとつではありませんが、「夫婦のすれ違い」も見過ごせない要因です。
たとえば、次のようなことに該当するパパはいませんか?
・赤ちゃんのお世話はママ任せ
・ママが疲れたというと「俺だって仕事で疲れてる」というだけで話を聞かない
・一日中家にいるんだから「疲れているなんて、甘えてるだけに違いない」と無意識のうちに決めつけている
ママは「赤ちゃんのために頑張らなきゃ」と無理をしがちです。そんな日々を過ごすなかで、パートナーである夫が理解してくれないと感じた瞬間に、孤独感や無力感が一気に押し寄せてしまうこともあるんです。
これを防ぐには、普段から思いやりを持ってコミュニケーションを図ることが欠かせません。
夫がママの産後うつの原因にならないための対策5選
パパが産後うつの原因にならないためにはどのようなことに気を配れば良いのでしょうか。今からできる対策を5つ紹介します。
ママを批判しない
「そんなことで泣くの?」「俺の方が大変」といった言葉は、産後とても敏感になっているママの心を深く傷つけます。
まずは「大変だったね」「頑張ってるね」と受け止めることから始めましょう。ママは今の気持ちや状況をパパに受け止めてもらいたいのです。
役割分担を見直す
育児や家事を「手伝うよ」と言っていませんか。「家事や育児はママの仕事」という前提があるからつい、そのような言葉が出てくる人も多く見られます。
夫婦で話し合い、家事も育児も「ふたりの仕事」と認識しましょう。できることから少しずつ役割分担を見直してみませんか。
周りに助けを求める
産後の大変な時期を夫婦だけで乗り越えようとすると、どちらかが限界を迎えてしまうこともあります。特にこの時期は「無理をしない」ことが大切です。
実家や地域のサポート、ファミリーサポート制度、宅配食やベビーシッターなど、使える支援を上手に活用しましょう。
夫婦で過ごす時間を持つ
赤ちゃん中心の生活の中でも、夫婦でほっとできる時間を意識的に作ることが大切です。
たとえば、子どもが寝た後のわずかな時間に「今日あったこと」を話すだけでも気持ちのつながりを感じられるでしょう。
専門家に相談する
ママの様子が「いつもと違う」と感じたら、専門機関へ相談するのも選択肢の一つです。
産婦人科や自治体、育児相談窓口など、相談できる場所はたくさんあります。「自分たちだけでなんとかしなきゃ」と考えず、早めに専門家に相談してみましょう。
産後うつの原因を防ぐには|夫に伝えたい、ママの本音
すべてのママが、必ずしも「パパにもっと手伝ってほしい」と思っているわけではありません。
- 話を聞いてほしい
- 気持ちに寄り添ってほしい
- 「ありがとう」と言ってほしい
それだけでママが救われることもあります。照れくさくてなかなか言葉に出せない時は、甘いものや美味しいものを買って帰ることからはじめてみるのもいいですね。
夫婦で寄り添い、産後の不安を乗り越えよう
赤ちゃんが生まれると、生活も感情も大きく変わります。
夫婦の関係も、今まで通りではうまくいかない場合もあるでしょう。産後は、夫婦ふたりで新しい形をつくっていく大切な時期でもあるのです。
思いやりを持ちコミュニケーションを取りながら、支えあって産後の時期を過ごすと夫婦の絆がさらに強くなるでしょう。
参考資料
[1]日本産婦人科医会
https://www.jaog.or.jp/qa/confinement/jyosei200311/