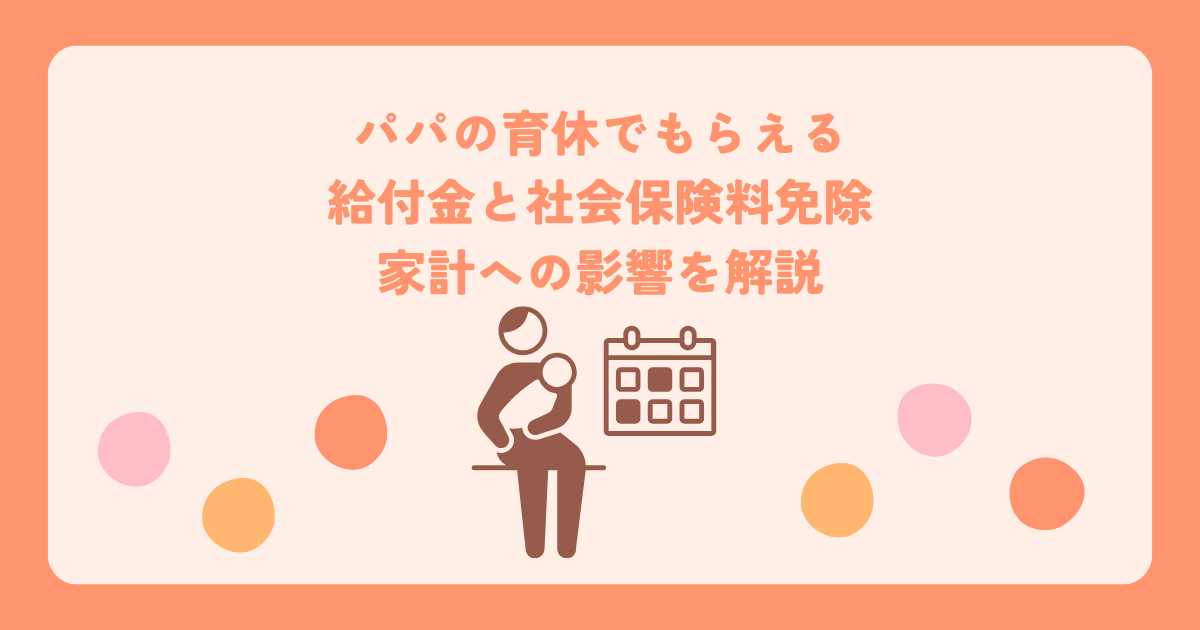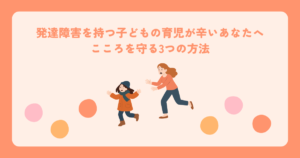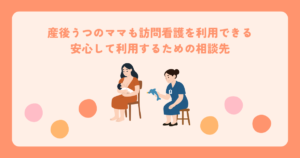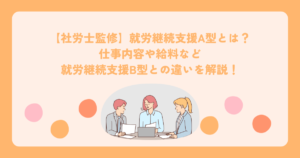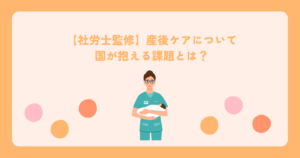パパが育児休業(育休)を取るとき、気になるのが家計への影響ではないでしょうか。「給付金はもらえるの?」「社会保険料はどうなる?」と不安になるパパは少なくありません。
この記事では、パパが育休を取得した際にもらえる給付金と、育休中に適用される社会保険料の免除制度をわかりやすく解説します。育休中の家計の不安を少しでも軽くしたい方は参考にしてください。
パパが育休を取るときの給付金について
育休中は会社からの給与が原則止まります。その際に支給されるのが「給付金」です。なお、会社によっては独自の手当がつく場合もあります。
パパが受けられる3つの給付金制度について見ていきましょう。
| 給付金の種類 | 内容 | 支給割合 |
| 出生時育児休業給付金(産後パパ育休) | 子の出生後8週間以内に育休を取得する場合に支給 | 6カ月までは休業前賃金の 67%、その後50%。 |
| 育児休業給付金 | 子が1歳未満の間に育休を取得した場合に支給。2回まで分割取得が可能 | 原則6カ月までは 67%、それ以降は 50%。 |
| 出生後休業支援給付金 | 上記の給付金を受ける方が両親ともに14日以上の育休を取るなど要件を満たした場合に追加で支給される※ | 13%(最長28日間) |
※配偶者が就労していない場合などは本人のみが対象
産後パパ育休給付金は出生後8週間以内、それ以降は通常の育児休業給付金に切り替わる形で利用可能です。出生後休業支援給付金(13%)は最長28日間、育児休業給付金などとあわせて支給されるため、最大で休業前賃金の約80%程度が補償されます。
育休中のパパが給付金を取得する条件
パパが育休給付金を受け取るには、いくつかの条件があります。主なものを紹介します。
- 指定された期日内に産後パパ育休を取得していること(子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能)
- 育休開始日前の2年間で、賃金支払基礎日数が11日以上ある月、または就業時間が80時間以上ある月が12カ月以上あること
- 育児休業を取得する期間中の就業日数が少ないこと(月に10日以下、または80時間以下)
- 有期雇用契約の場合は、契約が育休後も続く可能性があること
詳しくは厚生労働省の「育児休業等給付の内容と支給申請手続」を、合わせて参考にしてください。
給付金支給額の目安
通常の育児休業給付金は、休業開始前の賃金のおよそ 50〜67% の金額が支給されます。条件や休業期間によって変わるため確認しておきましょう。
令和7年4月に始まった「出生後休業支援給付金」では、この金額にさらに13%上乗せされます。28日が上限ですが、67%の給付金とあわせると80%となり、手取りと同等の金額が受け取れるケースもあります。
手続きの流れ
給付金の申請手続きの流れは次の通りです。
- 育休を会社に申し出る
- 事業主を通じてハローワークで「受給資格確認」などの手続き(必要書類を提出)
- 育休開始後、定期的に給付金の申請(通常2カ月ごと)を行う
ハローワークへの手続きや2カ月ごとの申請は、原則として会社が行います。早めに会社に育休を申請しておきましょう。
パパが育休中の社会保険料免除制度とは
パパが育休を取るときには、「保険料を払わずに済む」制度もあります。育児休業等の期間中に一定の条件を満たせば、健康保険・厚生年金保険の被保険者本人分も、事業主分も免除されます。[2]
免除期間
育児休業等を開始した日の属する月から、終了した日の翌日が属する月の前月までの期間が免除対象です。
なお、育休開始日と終了予定日の翌日が同じ月であっても、その月に14日以上育児休業等を取得していればその月の保険料は免除対象となります。
賞与(ボーナス)にかかる保険料
育休期間中に支払われる賞与についても、免除対象になる場合があります。令和4年10月から、賞与の支払月の末日を含む連続した1カ月を超える育児休業等を取得した場合が対象となりました。
手続きの方法
会社側が「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構や健康保険組合等に提出すると必要な手続きが行われます。
育休中のパパの給付金・社会保険料免除の注意点
給付金は「休業前の賃金」をもとに計算されます。残業代や手当の扱いによって金額が変わるので注意が必要です。また、育休中に働くと日数や時間、賃金の割合によっては給付金が減額されることがあります。
なお、給付金も社会保険料免除も会社を通じて申請が必要です。早めに会社に相談しておくと安心です。
パパの育休中には給付金や社会保険料免除があります
パパが育休を取ると給付金が受け取れ、さらに健康保険・厚生年金の社会保険料も免除されます。
制度の見直しにより、以前よりもパパが育休を取りやすい環境が整っています。これから赤ちゃんを迎えるパパは、会社に相談して条件を確認してみてください。制度を活用して家計の不安を減らし、安心して赤ちゃんとの時間を過ごしましょう。
参考資料
[1]厚生労働省│育児休業等給付について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html
[2]日本年金機構│令和4年10月から育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されました
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202210/100302.html