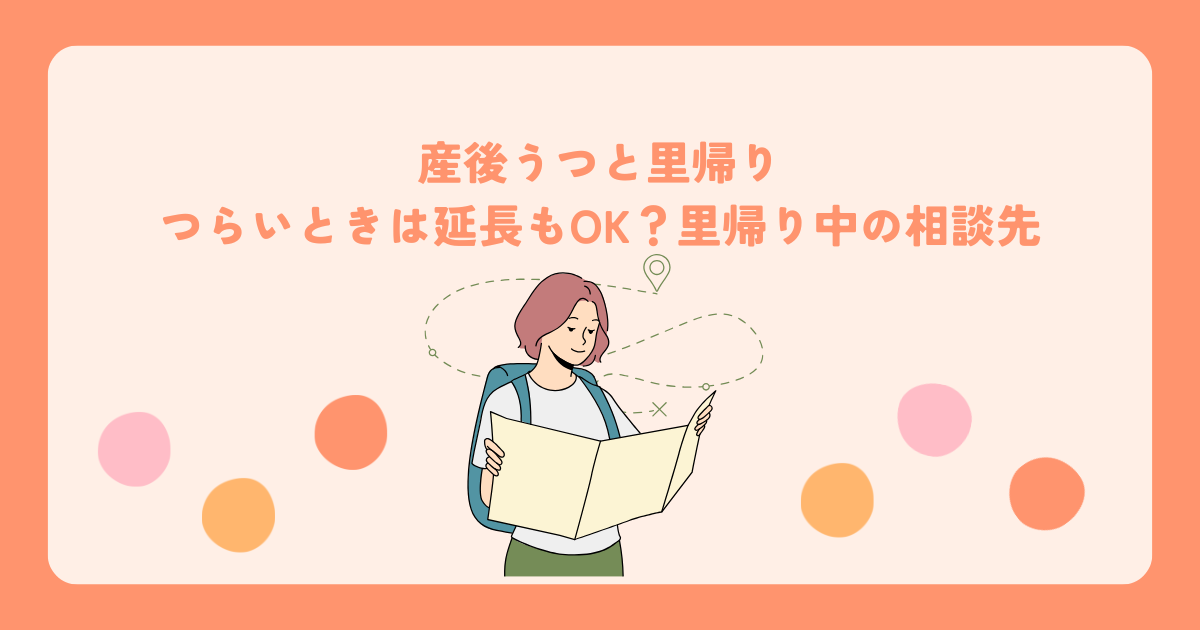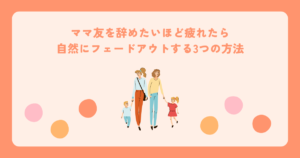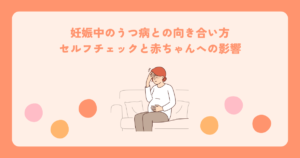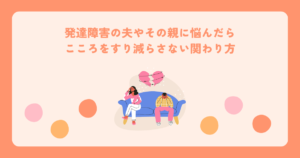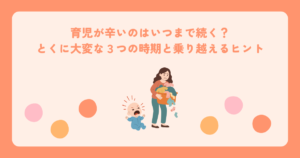「里帰りしてるのに、なんでこんなにつらいんだろう…」
実家にいるのにつらいなんて甘えかも…と、自分を責めてしまうママは少なくありません。
ただ、産後うつは里帰りの有無にかかわらず誰にでも起こりうるこころの不調です。
この記事では、里帰り中に産後うつになる背景や、つらいときの過ごし方、相談先についてご紹介します。
里帰り中にも産後うつが起こる理由
産後うつは、出産後のママのうち約10人にひとりが経験するこころの不調で、里帰りの有無にかかわらず起こるものです。
理由としては、次のようなものが挙げられます。
- 夜間授乳による寝不足
- ホルモンバランスの変化
- 実母の言動や昔ながらの価値観によるストレス
また、自宅にいる夫に申し訳なさを感じたり、実家のサポートなしで育児できるのか不安になったりすることもあるでしょう。
今は自分を責めず、あなたが安心できる環境でこころと身体を整えることを大切にしてください。
産後うつやマタニティブルーについて知りたいときは、こちらをあわせてご覧ください。
産後うつかも…と思ったら里帰りを延長する方法も
こころと身体がつらいときは、里帰りを延長するのもひとつの方法です。
ただ「本当は自宅に帰りたくない」と思っていても、次のような理由からムリをするママも少なくありません。
- 1か月で自宅に帰ると約束したから
- 実家に甘えず自宅に帰って家族で暮らさなきゃ
- 里帰りを延長すると両親に負担をかけて申し訳ない
産後間もない時期に大切なのは、安心して過ごせる場所で心身を休めることです。
こうするべきという思い込みにとらわれすぎず、今の自分にとってムリのない選択をしてください。
里帰り中に「産後うつかも」と思ったときにできること
里帰り中に「産後うつかも」と思ったときは、以下の対策をとりましょう。
自分を責めない
実家でサポートしてもらっているのに…と、自分を責めてしまうママも少なくありません。
ただ、ささいなことで不安定になりやすいのは、産後によくあるごく自然な反応です。
決してあなたの性格や感じ方の問題ではありません。
まずは自分を責めず「出産という大仕事をしたんだから、しばらくゆっくり休もう」と自分の気持ちにそっと寄り添ってくださいね。
夫に気持ちを伝えておく
産後は疲れやホルモンの影響で、イライラや不安が強くなりやすい時期です。
以下のように、自分の気持ちを夫に伝えましょう。
- 自宅で家事と育児をこなす自信がない
- まだ本調子じゃないから里帰りを延長するかも
- 自宅に戻るまでに赤ちゃんが寝る部屋を整えてほしい
前もって気持ちを伝えることで、夫側も赤ちゃんを迎える準備を整えやすくなります。
自宅に帰ってからの自分を助けるつもりで、遠慮せず夫に気持ちを伝えましょう。
実家の家族に理解してもらう
実家の家族に不安を打ち明けるだけでも気持ちが軽くなります。
以下のように、できるだけ具体的に伝えてみましょう。
- 授乳中はそっとしてほしい
- 寝不足のときもあるから朝はゆっくり休ませてほしい
- 場合によっては里帰りを延長させてもらうかもしれない
家族に理解してもらえないと感じるときは、保健センターや出産した病院に相談し、伝え方を一緒に考えてもらう方法もあります。
産後うつかもと感じたときの対処法についてもっと知りたいときは、こちらを合わせてご覧ください。
里帰り中の産後うつをひとりで抱えないための相談先
自宅とは違う地域に里帰りした場合「どこに相談すればいいの?」と戸惑ってしまうこともあるかもしれません。
まずは、里帰り先の自治体に相談しましょう。
保健センターや子育て支援課などの窓口に「現在〇市から里帰り中なのですが、産後の気持ちが不安定で…」と伝えれば、以下のような支援や相談先を案内してもらえます。
- 産後ケア事業(訪問や宿泊など)
- 育児やメンタルの相談窓口(保健師や助産師による対応)
一部の支援は、住民票がある自治体でしか利用できないことがあります。
その場合は、住民票のある自治体と連携してもらえる場合があるため、まずは相談することが大切です。
関連記事:気軽に頼れる産後うつ支援先|自治体のサポートや病院以外の選択肢
famitasuのオンラインカウンセリングでは、ご自宅からどのような悩みもご相談いただけます。オンラインやチャットに対応しているため、ぜひお気軽にご利用ください。
産後うつは里帰り中にも起こるからこそ、あなたの気持ちを大切に
産後うつは、里帰り中も起こりうるこころの不調です。
サポートしてもらっているのに…と自分を責める必要はありません。
大切なのは、あなた自身が安心して過ごせる場所でこころと身体をゆっくり休めることです。
迷いや不安があるときは、夫や家族に気持ちを伝えたり、自治体の相談窓口に頼ったりして、不安をひとりで抱えないようにしましょう。
身近な人には言いづらいときや、誰に相談すればいいかわからないときは、famitasuのオンラインカウンセリングをご活用ください。