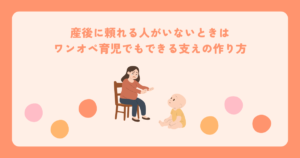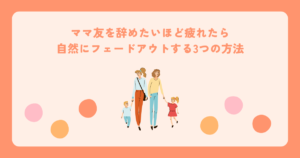「赤ちゃんが生まれて幸せなはずなのに、なぜか涙が出る」そんな気持ちを抱えているママは少なくありません。産後はホルモンバランスの乱れや生活リズムの乱れから、うつになりやすい時期とも言われています。
この記事では「産後うつ」の割合、なりやすい人の特徴、そして自分でできる対策について、わかりやすくお伝えします。
産後うつとは?
産後うつとは、出産後に起きるうつ症状を指します。
ママのこころに起きる変化
出産後は、ホルモンバランスの急激な変化もあり、心と体に大きな負担がかかります。出産の疲れが取れないまま育児が始まり、プレッシャーや寝不足、孤独感が重なるため心が不安定になってしまうママも。
「赤ちゃんのことは大事。でも、なぜか無力感が消えない」 そんなふうに感じるのは、決して珍しくありません。
産後うつと「マタニティブルーズ」の違い
出産直後に一時的に情緒不安定になることを「マタニティブルーズ」と言います。産後のママの30~50%が経験するもので、多くの場合、出産後数日〜2週間ほどで自然と落ち着きます。[1]
一方、「産後うつ」は、それよりも症状が深刻で2週間以上長引くのが特徴です。「毎日つらい」「赤ちゃんが寝ているのに眠れない」などの状態が2週間以上続く場合は、産後うつの可能性も考えられます。
産後うつの割合はおよそ10%
厚生労働省の研究データによると、日本では産後うつを経験するママは全体の約10%でした。およそ10人に1人が産後うつを経験しているということになります。
また、産後うつになるパパもおよそ10%です。[2]
産後うつになりやすい人の特徴とは
産後うつになりやすい人には共通する特徴があります。主なものを見ていきましょう。
真面目・頑張り屋な性格
「ちゃんとしなきゃ」「いいお母さんにならなきゃ」と、完璧を求めて頑張りすぎてしまうママほど、自分を追い込みがちです。
育児や家事のサポートが少ない
頼れる人がいないため、ひとりでなんでもしなければならない場合も、心の負担が大きくなります。
過去にうつ症状を経験している
これまでにうつ症状を経験した人は、産後うつを再発しやすい傾向があります。妊娠中から定期的に受診をしたりカウンセリングを受けたり、慎重にケアしておくのが大切です。
睡眠不足や体の不調を抱えている
出産後は頻繁な授乳やおむつ替えが必要で生活リズムが崩れがちです。 慣れない育児と疲労が重なり、回復する間もなく心も限界に近づいてしまうケースがあります。
長時間労働│パパの場合
パパの場合は育児による睡眠不足と長時間労働が重なることが産後うつの主な要因となることが少なくありません。パパの産後うつについては知らない人も多く、言い出せないパパもいるでしょう。
自分でできる産後うつの予防と対策
「すぐに涙が出る」「赤ちゃんが可愛いと思えない」「食欲がわかない」そんな日々が続いているママやパパは産後うつかもしれません。
ここでは、今からでもできる産後うつの予防と対策を4つお伝えします。
赤ちゃんを育てるのは簡単ではありません。ママもパパも、ぜひ、できるところから取り入れてみてくださいね。
ひとりで抱え込まない
「私が1人で頑張らなきゃ」と思いつめていませんか。誰かに話を聞いてもらうだけでも、心が軽くなることってありますよね。家族や友達などまずは身近な人に気持ちを話してみましょう。
話せる人・相談できる場所を見つける
ママ友や保健師さん、SNSのコミュニティなど、さまざまなつながりがあるでしょう。顔の見えない相手でも、話しをするだけで安心できることもありますよ。
パートナーや家族への協力依頼
誰かに「助けて」と伝えるのは、弱さではありません。赤ちゃんを育てるにはパートナーや家族との協力が欠かせません。今しかない大事な時期だからこそ、少しだけでも周りに頼ってみてくださいね。
地域のサポートを活用する
市区町村の保健センターや子育て支援拠点では、定期的な育児相談を行っているところもありますよ。児童センターなど、予約せずに行ける場所もあるので、まずは自治体のホームページなどを調べてみてくださいね。
つらいと感じたら早めの相談を
「なんとなくつらい」「どうしたらいいかわからない」そんな風に思っているのなら、一度専門家に相談してみませんか。
産婦人科や心療内科、小児科で相談に乗ってくれますよ。自治体の相談窓口に連絡してみるのもおすすめですよ。
産後うつは10人に1人│抱え込まずに相談しましょう
産後うつになるのは、決して「あなたが弱いから」ではありません。多くのママやパパが、同じように戸惑い、悩んでいます。
つらい気持ちをひとりで抱えこむ必要はありません。身近な人や専門家に相談してみましょう。きっと解決策が見つかります。
参考資料
[1]公益社団法人日本産婦人科医会
https://www.jaog.or.jp/qa/confinement/jyosei200226
[2]国立教育医療研究センター
https://www.ncchd.go.jp/scholar/assets/7a9c3db5c293e8016ca72df23efe9877.pdf