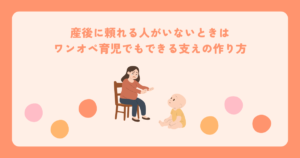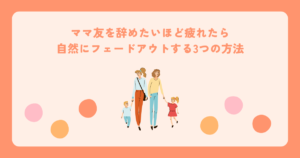「もしかしたら産後うつかもしれない」
「この程度で病院を受診していいのかな?」
育児や体調に不安を抱えながらも、受診のタイミングに迷う方は少なくありません。
この記事では、産後うつの受診を検討する目安や相談できる診療科、病院以外で相談できる場所について解説します。
「まだ大丈夫」と思っていても、こころが限界を知らせているサインが出ているかもしれません。
この記事があなたの判断を助けるきっかけになれば幸いです。
産後うつで病院を受診する目安
気分の落ち込みが長引く場合や育児に支障が出ている場合は、病院の受診を検討することが大切です。
以下のような症状が見られる場合は、病院を受診する目安としてとらえましょう。[1]
- 自分を責め続けてしまう
- 自分を傷つけたい気持ちになる
- 子どもが可愛いと思えない、愛情がわかない
- 2週間以上、気分の落ち込みや無気力が続いている
- 眠れない・食欲がないなど、身体的な症状が出ている
- 子どもに強く当たってしまいそうで怖いと感じることがある
とくに厚生労働省では、以下2つの質問に「はい」と答える場合、産後うつの可能性が高いとされています。[1]
- この1か月間、気分が沈んだり、憂うつな気持ちになったりすることがよくあった
- この1か月間、物事に対して興味がわかない、あるいは心から楽しめない感じがよくあった
こうした指標は、受診のタイミングを判断するうえでの目安になります。
少しでも心当たりがあると感じたら、早めに専門機関へ相談しましょう。
受診の目安について詳しく知りたいときは、こちらの記事を合わせてご覧ください。
産後うつで受診できる診療科
産後うつが疑われる場合、以下のような診療科が相談先になります。
心療内科・精神科
精神的な不調が生活に支障をきたしている場合に、専門的な診断とサポートが受けられます。
薬物療法だけではなく、心理療法やカウンセリングの相談も可能です。
産婦人科
身体の回復やホルモンの変化もふまえて、こころと身体の両面から相談したいときに適しています。
助産師への相談を受け付けている病院もあるため、希望するときは予約時に「助産師に相談したい」と伝えましょう。
小児科・乳幼児健診
子どもの診察や健診のついでに、ご自身の体調や気分、育児の不安などについて相談しやすい場所です。
とくに乳幼児健診では、育児の不安やこころの不調に気づいてもらいやすく、必要に応じて適切な専門機関を紹介してもらえます。
相談できる診療科についてもっと知りたいときは、こちらの記事を合わせてご覧ください。
産後うつで早めに受診するのが有効な理由
産後うつの症状に気づいたら、できるだけ早めに医療機関を受診しましょう。
放置することで育児や夫婦関係への悪影響が出たり、自ら命を絶ってしまったりするなど、深刻な問題につながる可能性があるためです。[1]
早期に医療機関を受診し早めに必要な治療を受けることで、回復までの期間が早まったり症状が軽減したりしやすいとされています。
産後うつは出産した女性の10〜15%に起こるといわれ、決してあなたの甘えや弱さが原因ではありません。
ムリせず早めに医療機関に相談することで、こころと身体の回復がスムーズに進みやすくなるでしょう。
産後うつで病院を受診するのが不安なときは
「精神科に行くのは少し抵抗がある」「薬に頼りたくない」という気持ちを抱える方も少なくありません。
ただ、医療機関を受診したら必ず薬が処方されるとは限らず、以下のような薬以外の治療法が選択されることもあります。
- カウンセリング
- 生活環境の見直し
- 認知行動療法のような心理療法
対応は医療機関によって異なるため、不安なことはあらかじめ伝えておきましょう。
どうしても医療機関に行きづらい場合は、お住まいの地域の保健センターを利用する方法があります。
保健センターは全国の市区町村に設置されており、保健師や助産師などの育児とこころのケアに詳しい専門家に相談できる場所です。
インターネットで「〇〇市 保健センター」と検索すると、最寄りの窓口を確認できるため、まずは検索してみてください。
あなたが「つらい」と思ったときが産後うつの受診の目安
もしかして産後うつかも…と感じたときは、あなたのこころが助けを求めているサインです。
「これくらいで病院に行っていいの?」「まだ甘えてるだけでは?」と感じてしまうかもしれませんが、あなたがつらさを感じたときはムリせず医療機関を受診しましょう。
支援が少ない状況でがんばりすぎると、自分の状態を正しく見つめるのが難しくなります。
もしかして…と思ったら、あなたが相談しやすい窓口を利用して気持ちを話してみてください。
famitasuでは、産後のメンタルヘルスに詳しい専門家によるオンラインカウンセリングを行っています。ひとりで抱え込まず、つながりの中でこころを守っていきましょう。
[1]厚生労働省
第5章 養育者のメンタルヘルス
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000520616.pdf?utm_source=chatgpt.com