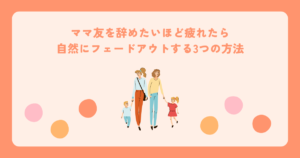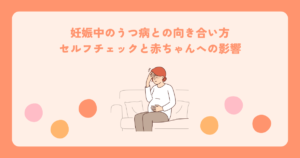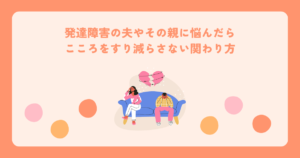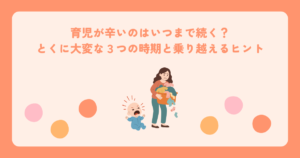産後うつかも…と思っても、ひとりで抱え込んでしまうママは少なくありません。
病院に行くのは抵抗があるけど、誰かに助けてほしいときに役に立つのが、自治体や専門機関による支援です。
この記事では、全国で受けられる産後うつ支援や、気軽に相談できる窓口をご紹介します。
そばで支えているご家族の方にもお読みいただけたら幸いです。
産後うつには周囲の支援が欠かせない
産後うつは決して甘えではなく、専門的な支援が必要な状態です。
出産後の女性のうち約10%が産後うつになるとされ、誰にでも起こりうるこころの不調といえます。[1]
実際に支援を受けて産後うつから回復したママの中には「最初は抵抗がありましたが、他のママが支援を受けている様子を見て、私も頼ってみようと思えました」と語る方もいます。[2]
産後うつについてもっと知りたいときは、こちらの記事を合わせてご覧ください。
全国の自治体による産後うつ支援
全国で実施されている産後うつ支援として、以下が挙げられます。
乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)
乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)とは、生後4か月までの赤ちゃんがいる家庭に保健師や助産師が訪問し、ママと赤ちゃんの様子を見守る制度です。[3]
ママの体調や育児の悩みを聞いてもらえるほか、ちょっとした不安を話すきっかけにもなります。
必要に応じて、医療機関や地域のサービスを案内してもらえます。
産後ケア事業
産後ケア事業とは、出産後のママが心身を休められるように、助産師や保健師が育児の相談や心身のケアなどを行う制度です。[4]
宿泊型やデイケア型、訪問型などがあり、内容や利用方法は自治体によって異なります。
自己負担が必要な場合もありますが「ちょっと休みたい」「話を聞いてほしい」と感じたときに頼れる支援のひとつです。
EPDS(産後うつ簡易チェック)
EPDS(エジンバラ産後うつ病自己評価票)は、産後のこころの状態を確認するための質問票です。
一部の自治体では、1か月健診や家庭訪問の際に導入されていて、点数が高い場合には保健師や助産師から支援の提案がされるケースもあります。
EPDSで自分の状態をチェックしたいときは、こちらの記事を合わせてご覧ください。
病院以外で受けられる産後うつ支援
「病院に行くほどではないけど誰かに気持ちを聞いてほしい」というときには、以下の場所を利用しましょう。
子育て支援センター
おもちゃや絵本などが置かれたプレイルームで赤ちゃんを遊ばせながら、保育士にちょっとした悩みを相談できる場所です。
育児中のママとも出会えるため、ひとりじゃないと感じられるきっかけになるでしょう。
「○○市 子育て支援センター」と検索して、お住まいの地域の窓口を調べてみてください。
日本助産師会による電話相談
日本助産師会では、毎週火曜日の10時〜16時に助産師による無料の電話相談を行っています。[5]
授乳や育児の不安など、気になることを気軽に相談できる窓口です。
全国の都道府県でも同様に、助産師による相談事業が実施されています。
ちょっと話すだけでこころが軽くなることもありますが「もっとじっくり話したい」「今の気持ちを整理したい」と感じたときは、famitasuのオンラインカウンセリングを利用ください。
産後のこころに詳しい専門家が、あなたのペースでお話をお聴きします。
親子のための相談LINE
厚生労働省とこども家庭庁が提供する「親子のための相談LINE」は、匿名で利用できるチャット相談窓口です。[6]
子育て中の悩みや不安、気持ちの落ち込みなどを、専門の相談員がやさしく受け止めてくれます。
famitasuでは、育児やメンタル不調の経験がある専門家とのチャットカウンセリングをご利用いただけます。ぜひお気軽にお問い合わせください。
家族や周囲の人ができる産後うつ支援
産後うつのママにとって、家族や身近な人の存在は大きな支えになります。
育児中に不安や孤独を感じているとき、誰かがそばにいてくれると感じられるだけでも安心感につながるものです。
ただ、心配されすぎたりムリに励まされたりすると、プレッシャーになることがあるため、そっと寄り添う姿勢を大切にしましょう。
たとえば、以下のような関わりがママの不安をやわらげる助けになります
- 「ママ、休めてる?」とやさしく声をかける
- 家事や育児を引き受けてママに休んでもらう
- 自治体の支援制度や相談窓口を代わりに調べる
特別な言葉や行動がなくても「気にかけているよ」という気持ちは、確実にママに届きます。
身近な人だからこそできる日々の支援が、ママをそっと支えてくれるのです。
まとめ
産後うつは誰にでも起こりうるこころの不調で、決して特別なことではありません。
出産や育児の大きな変化の中で、心が揺らぐのは自然なことです。
つらいときはひとりでがんばりすぎず、自治体や専門機関の支援を利用しながら、少しずつ自分らしさを取り戻していきましょう。
[参考資料]
[1]日本産婦人科医会
https://www.jaog.or.jp/qa/confinement/jyosei200311
[2][3]高橋秋絵
産後うつ状態の母親はどのような経験をしたのか
2.産後うつ状態の母親の経験
9)【回復に導いてくれたものがあった】
[3]厚生労働省
乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)の概要
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/kosodate12/01.html
[4]厚生労働省
産後ケア事業の実施状況及び今後の対応について
https://www.mhlw.go.jp/content/11908000/001076325.pdf
[5]日本助産師会
https://www.midwife.or.jp/general/consultation.html
[6]子ども家庭庁
親子のための相談LINE
https://www.cfa.go.jp/policies/jidougyakutai/oyako-line?utm_source=chatgpt.com