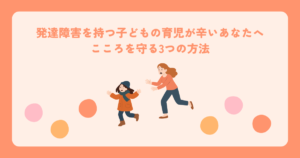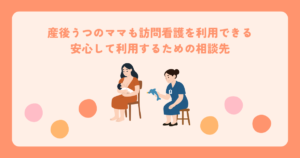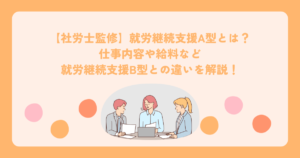長時間労働やハラスメント、人間関係の悩みによってメンタルヘルス不調を訴える社会人は年々、増加傾向にあります。
「体調は悪いけど、退職をすると収入面が心配・・」「有休の日数も限られているし・・」などの理由で不調を感じながらも退職はできず、仕事を休むこともままならない。
そのような悩みを抱えながら、仕事を続けている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は「休職」をする場合の手続きや注意点、生活の保証についてどのような制度があるのかを社会保険労務士、社会福祉士としてメンタルヘルス不調を抱える社会人のサポートをしている筆者がご説明をさせていただきます。
「休職」という選択肢もご検討いただける一助になりましたら幸いです。
統計から見るメンタルヘルス不調による休職者の傾向
職場での人間関係の悩み、または長時間労働による心身の疲れの蓄積がきっかけになり、ストレス性の疾患を発症するケースが多くなっています。
令和4年労働安全衛生調査(厚生労働省)の結果によると、過去1年間(令和3年11月1日~令和4年10月31日)にメンタルヘルス不調により連続1カ月以上休業した労働者がいた事業所の割合は「10.6%」となっており、令和3年調査「8.8%」から1.8%増加しています。

(参照)令和4年労働安全衛星調査(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/r04-46-50_kekka-gaiyo01.pdf
「退職はせずに少し仕事を休んで療養したい」という時に「休職」について検討を始めると思います。
今回は「休職」の制度について正しく理解することで、安心して仕事を休みながら心身の回復を図れるようにするための必要な情報を簡潔にお伝えしていきたいと思います。
まずは休職について知りましょう!
会社で働くパパ、ママの立場から考えると「休職して会社に迷惑をかけたくない・・」「休んでいる間の家族の生活が心配・・」という不安を感じるのは当然のことだと思います。
では、そもそも「休職する」というのはどのような状態のことを指すのでしょうか?
答えは「会社との雇用契約を継続したまま休むこと」です。
「退職」の場合は雇用契約が終了しています。一方で「休職」の場合には雇用契約が継続しており会社に在籍している状態ですので、例えばお子様を保育園に継続して通わせることができますし、ご自身が仕事が出来る状態まで回復すれば会社への「復職」を検討することもできます。
心身の不調により「もう、会社を辞めようかな・・」と考える前に、「休職」という選択肢も検討すると良いかもしれません。
休職する時の手続きは何が必要?会社への相談だけでOK?
休職までの流れ(病院・会社)
休職をするまでの流れは以下の通りです。
①医師による診察
医師の診察により、休職が必要な状態であるかを判断します。
②診断書の発行
診断書には「病名」「症状」「休職期間」などが記載されます。会社指定の記載内容が必要な場合もありますので、事前に社内で確認しておくとスムーズです。
③職場と休職について相談する
①の前に職場に相談するのが難しい場合、診断書を基に状態を説明し、今後について相談を行います。
④休職準備
③の相談の結果、業務の引継ぎやPC等の会社備品の返却など、社内ルールに従って手続きを進めます。産業医が在籍している会社では、産業医との面談が実施されることもあります。
⑤休職
休職までの流れ(健康保険/傷病手当金)
休職をする際に一番の気がかりになるのは、お金の問題という方は多いと思います。
傷病手当金は、業務外の病気やケガを理由に休職した際に受給できる給付金のことです。
休職制度は会社によってさまざまですが、一般的には休職中に給料が支払われる会社は多くありません。
傷病手当金は、療養のために会社の給与が受給できなくなった方の生活を保証するもので、メンタルヘルス不調での休職にも支給されます。

支給要件
傷病手当金の支給要件は以下の通りです。
・業務外の病気やケガで療養中であること
・療養のための労務不能※であること
※労務不能:被保険者が今まで従事している業務が出来ない状態のことで、労務不能であるか否かは、医師の意見及び被保険者の業務内容やその他の諸条件を考慮して判断します。
・4日以上、仕事を休んでいること
療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間(待機期間といいます)を除いて、4日目からが支給対象になります。
・給与の支払いがないこと
ただし、給与の一部だけ支給されている場合は、傷病手当金から給与支給額を減額して支給されます(差額支給)
(参考)傷病手当金について(全国健康保険協会)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307/
支給額
支給額はざっくりというと給料の3分の2程度です。
具体的な計算方法は以下の通りですが、聞きなれない用語もあると思いますので、用語の簡単な解説と全国健康保険協会の該当ページのリンクをご案内させていただきました。
詳細をご確認される際には、ご参照ください。
・1日当たりの金額:「支給開始日」※1の以前12カ月の各「標準報酬月額」※2を平均した額 ÷30日×3分の2
※1「支給開始日」とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです。
※2「標準報酬月額」とは、被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りのいい幅で区分したものです。第1級から第50級の区分があります。
(参考)標準報酬月額・標準賞与額とは?(全国健康保険協会)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1962-231/
支給期間
同一の傷病については、支給開始日から通算して「1年6カ月」です。
今回の記事では「全国健康保険協会(協会けんぽ)」を例にご説明させていただきましたが、大企業が加入している「健康保険組合」では独自の規定を設けているケースもあります。加入されている健康保険の規定をご確認の上、申請をしていただくようお願いします。
傷病手当金は被保険者(従業員)自身からの申請が必要です。申請方法については、各健康保険へのご確認ください。
休職中の過ごし方は?
休職中は仕事から離れて、しっかり休むことが大切です。
主治医の指示のもと、定期的な通院と服薬での治療を行い、心身の回復を最優先に考えて療養します。
休職中のフォローアップとして、会社の人事担当者や産業医から定期連絡がある場合には、事前に決めた連絡方法(電話、メールなど)によって、治療の経過や今後の見込みについて確認をしたり、不安や悩みを相談することができます。
会社側からも社内の支援体制について説明がされるなど、お互いに情報共有の場として活用することが望ましいです。
ただし「約束した時間に連絡がつかない」、「メールに返信がない」という状況にはならないよう気を付けましょう。
また、小さなお子様がいらっしゃる場合には「会社を休んでいるんだから、子どもと一緒に過ごさないと」と思いがちですが、「今の自分には休養が必要」と割り切って生活をするように心掛けましょう。休めるときに長期間休むことによって、心身の回復を図り、更に再発の予防にもなります。
体調が整ってきたら、軽い散歩や買い物などで外出をして体を動かすことも大切です。
心身の回復には、体力も必要ですからね。
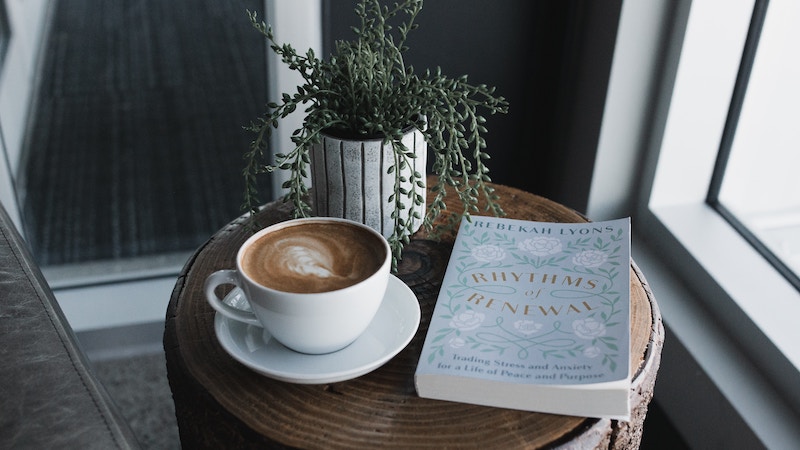
職場復帰、復帰後のフォローアップ
職場復帰については、以下5つのステップで進められます。
①主治医による職場復帰可能の判断
自己判断で復職を決めるのではなく、主治医の専門的な判断と診断書が必要になります。会社へ職場復帰を希望する旨を伝え、診断書を提出します。
②職場復帰の可否の判断、及び職場復帰支援プランの作成
会社側では、診断書の内容を参考に産業医、人事担当者、職場の上司など関係者で復職の可否を判断します。本人の意向を確認後、復職が可能と判断された場合は「職場復帰支援プラン」を作成します。
③最終的な職場復帰の決定
「職場復帰支援プラン」に基づき、復職後の就業条件(復職開始日、勤務場所、勤務時間、業務内容など)をお互いに確認した上で、復職を決定します。
⑤職場復帰後のフォローアップ
「職場復帰支援プラン」に基づき、必要な就業上の措置、及び治療への配慮を実施します。
病状は変化がありますので、必要に応じてプランの見直しも行います。
メンタルヘルスに関する健康情報は機微な情報になりますので、例えば「通院日」などの必要最小限の範囲に限定した情報の共有と業務調整をしていきます。
まとめ
休職について解説をさせていただきましたが、例えばメンタルヘルス不調の原因が「部署の人間関係」の場合は部署異動で解消されたり、「長時間労働による疲労の蓄積」が原因の場合には業務量の調整で負担が緩和される可能性もあります。
休職も一つの選択肢として捉え、ご自身の希望に合った選択をすることが望ましいと思います。
今回の記事が休職を検討するパパ、ママの情報整理と選択肢を考える上でのご参考になれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!