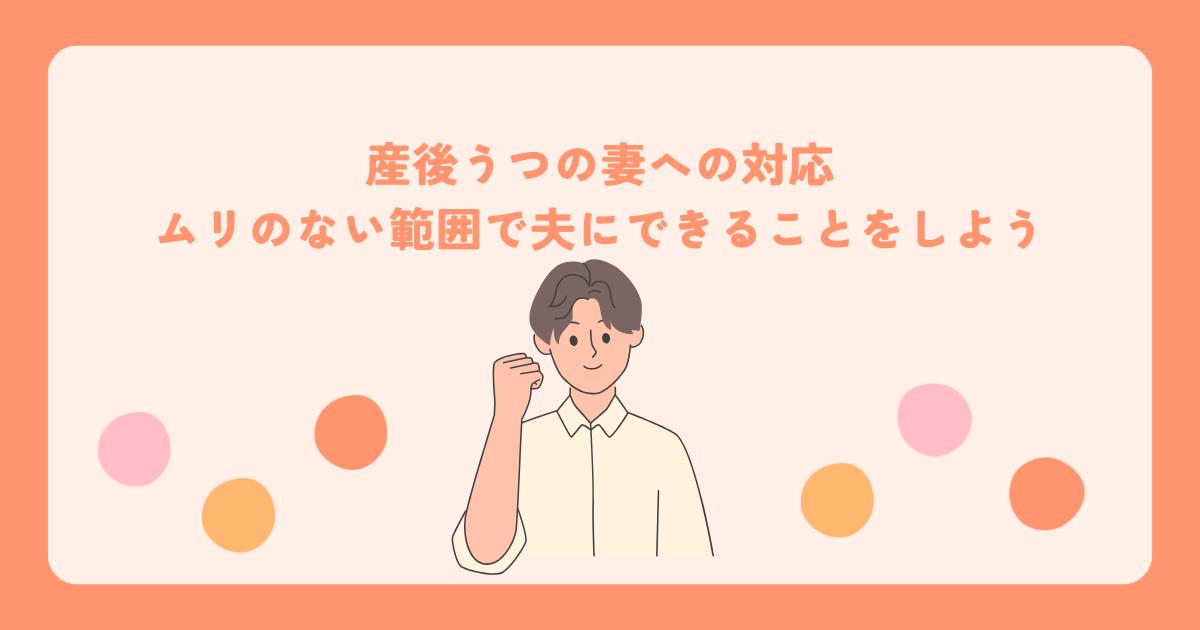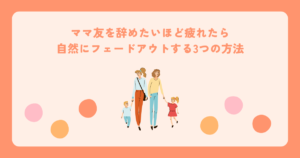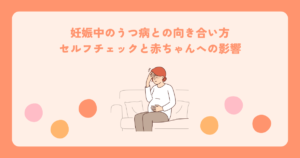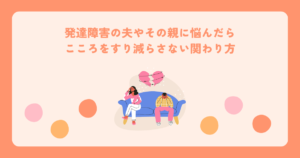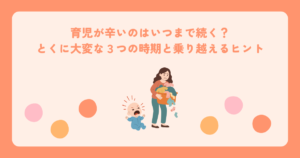産後うつは産後3か月以内に発症し、気分の落ち込みや自己評価の低下などがみられるものです。
産後はメンタルが不安定になりやすいため、妻の様子に戸惑う夫も多いでしょう。
この記事では、妻が産後うつかチェックする方法や夫が妻にできることなどについて解説します。
子育て中の妻の本音を知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
子育ての大変さがわからない旦那の傾向と対策|協力に導くコツ2選
10人にひとりが経験する産後うつ
産後うつは約10人にひとりが経験する病気で、決して珍しいものではありません。[1]
以下のような理由から、産後は心身のバランスを崩しやすい時期です。[2][3]
- 産後で体力が低下する
- 夜間授乳により睡眠不足になる
- 女性ホルモンが急激に低下する
参考:産後のメンタルが不安定になる理由|セルフチェックや乗り越え方3選
とくにうつ病の経験がある方や夫・実家など周囲のサポートが得られにくい方は、産後うつのリスクが高まるとされています。
産後はママ自身の体調が回復していない状態で24時間赤ちゃんのお世話をするため、周囲の手厚いサポートが必要です。
妻が産後うつかどうかチェックする方法
妻の様子を思い返し、以下に心当たりがあるか確認しましょう。
- 気分が沈んでいる
- ものごとへの興味がなくなっている
- 楽しいと感じていたことを楽しめなくなっている
参考:産後のメンタル不調は病院へ|症状チェックで知る受診の目安と相談先
このような症状を1日中感じる状態が2週間以上続くときは、産後うつの可能性が高いと考えられます。
ただ、気持ちが落ち込む時間が短く、趣味や育児を楽しむ様子があれば、産後うつの可能性は低いとされています。[4]
産後うつの妻に夫ができること
産後うつの妻に夫ができることは以下のとおりです。
- 妻に対する声かけを忘れない
- 冷静になれるコミュニケーション方法を選ぶ
- 自分自身の感情を大切にする
ひとつずつ確認します。
妻に対する声かけを忘れない
産後は赤ちゃん中心の生活になりますが、妻への声かけを忘れないようにしましょう。
子どもが1歳半の時点で相談しやすい夫婦関係を作れていると、母親の育児に対する自信が高まることがわかっています。[5]
相談しやすい関係をつくるためには、ママは寝られた?と妻を気遣う声かけをしたり感謝を伝えたりすることが大切です。
赤ちゃんが生まれると周囲の関心は赤ちゃんに集まるため、母親は誰にも弱音を吐けないことが少なくありません。
夫が自分を気にかけてくれているという安心感があるだけで、妻の大きなこころの支えになるでしょう。
冷静になれるコミュニケーション方法を選ぶ
冷静にコミュニケーションを取れる方法を選びましょう。
産後は夫の何気ない一言や気遣いにさえ過剰に反応してしまうことがあります。
よかれと思った発言で妻が泣いたり怒ったりして、どうしたらよいかわからなくなる夫も少なくありません。
会話やLINE、交換ノートなど、妻の負担が少なく冷静にコミュニケーションを取れる方法を検討してください。
体調の回復や子どもの成長により、妻の精神的な負担はラクになるため、状況に合わせてコミュニケーション方法を変えていきましょう。
自分自身の感情を大切にする
夫であるあなた自身の感情を大切にしてください。
産後1年以内に精神的な不調を感じる母親は10.8%ですが、父親も11.0%がメンタル不調を感じることがわかっています。
参考:父親も産後のメンタルに悩みやすい|セルフチェックで早めに対処しよう
産後は妻のサポートが大切な時期ですが、夫が我慢すればよいというわけではありません。
あなたが疲れたときは周りに頼りながら、ムリのない範囲で家族をサポートしていきましょう。
産後うつの妻を持つ夫が相談できる場所
産後うつの妻が心配なときや育児のストレスがつらいときは、精神科や心療内科に相談してください。
精神科や心療内科は家族からの相談にも応じていることが多いですが、事前に確認すると安心です。
病院を受診する時間がとれないときは職場の産業医や、子ども家庭庁が実施している「親子のための相談LINE」を頼りましょう。
親子のための相談LINEは、18歳未満の子どもやその保護者が匿名で相談できる窓口です。
famitasuではオンラインやチャットで専門家へ相談できるため、ぜひお気軽にご利用ください。
まとめ|産後うつの妻にムリのない範囲でサポートしよう
産後うつは約10人にひとりが経験する病気で、決して珍しいものではありません。
産後うつは周囲のサポートが受けられないことでリスクが高まるため、妻をサポートすることが大切です。
ただ、産後1年間は夫のメンタル不調のリスクが高まる時期でもあります。
夫であるあなた自身の感情を大切にしながら、ムリのない範囲で妻をサポートしましょう。
ストレスがたまりつらいときは、famitasuのオンラインカウンセリングをご利用ください。
あなたのどのようなご相談もお待ちしております。
参考資料
[1]日本産婦人科医会
https://www.jaog.or.jp/qa/confinement/jyosei200311
[2]働く女性の心とからだの応援サイト
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/health/column-22.html
[3]日本産婦人科医会
https://www.jaog.or.jp/qa/confinement/jyosei200226
[4]厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000520616.pdf
[5]育児期にある夫婦ペアレンティング
―互いの育児の批判をめぐって―
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjam/advpub/0/advpub_JJAM-2019-0009/_pdf